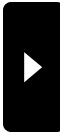2013年02月28日
脳を活性化して勉強を

さて今回は、テスト勉強にスパートをかける時期といういことで、
テスト勉強に役立つ情報をお伝えします。
「勉強をしようと思って机に向かうんだけど、なかなか取り掛かれない」
というセリフを、生徒からよく聞きます。
ついつい漫画本に手が伸びてしまったり、音楽を聞き入ってしまったり、
ボーッとしてしまったりして、勉強に集中出来ないというのです。
そこで、集中力を高めた状態で勉強を開始できる方法をお伝えしたいと思います。
それは、“単純計算”をするか、“音読”をすることです。
最近の脳科学の研究から、難しい問題を考えている時よりも、
一桁の足し算などの単純計算や音読をしている時の方が、
脳の多くの部分が活発に動くということが解明されています。
ですので、“単純計算”や“音読”を数分行い、
脳が活発に活動している状態に してから勉強に取り掛かると、
その後の効率がアップする可能性が高いです。
小学生など、勉強に目的意識を持つことが難しい年齢のお子さんにも効果的で、
「100マス計算」をやらせてから授業に入ると、
スムーズに導入出来ることが多いです。
その際、タイムを計っておき、それを縮めていくこを
自信につなげて欲しいという意味合いもあるので、一石二鳥です。
音読の場合は、これから取り組もうとしている問題を読ませることで、
強制的に対象に興味を集中させられるので、こちらもオススメです。
れでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月27日
親業は大変だ

現在の家庭教師でも実施しておりますが、
学習塾時代にも、定期保護者面談を年3回実施しておりました。
この時期は、もうすぐ3月、新年度に向けての第1回面談の時期です。
保護者面談をさせていただくと、毎回のように再確認することがあります。
それは、“やっぱり子育ての絶対的主役は、親御さんしかあり得ないんだな”ということです。
子育てには、予行練習がありませんから、いつもぶっつけ本番です。
皆さんそれぞれに自信と、不安と、期待を抱えていらっしゃいます。
思春期を迎えたお子 さんの全てを把握することは
不可能です(その必要もないと思います)が、それでもやはり、
ここまでのお子さんの人生を一番長く見てきたのは、紛れもなく親御さんです。
そして、お子さんの人生に一番影響を与えているのも、紛れもなく親御さんです。
普段、教場でお子さんを見ていて、面談で親御さんにお会いすると、
いつ もそんなことを深く実感します。
私に言われるまでもないことだと思いますが、
ご自身のお子さんに対する影響力の強さを、改めて自覚されることをゴテイアンいたします。
何にしても、“親業”というのは本当に大変ですが、
ちょっとしたコツや、パラダイムを変えることで、
お子さんの将来が変わることがあります。
以前に、「親力で決まる子供の将来」というメルマガを紹介しましたが、
このようなツールも使って見識を広め、参考にしていくことで、
よりバランスの良い選択が出来るので はないかと考えておりますので、
改めてご紹介いたします。
バックナンバー:http://yohei.biz/t/oyaryoku-b
また、このメルマガの集大成が単行本としても出版されておりますので、
ご一読されることをオススメします。
「親力で決まる!子供を伸ばすために親にできること」
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月26日
1年生になる前に準備したいこと

『1年生になる前に準備したいこと』
今回の投稿では、
以前に私が作成したレポートを共有させていただこうと思います。
上記タイトルリンクをクリックして、ご覧ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
さて、このレポートでは、
学習塾教室長を10年以上務めてきた経験から、
就学前のお子さんをお持ちの親御さんに、
1年生になる前に身につけておきたい力についてお伝えします。
この年頃のお子さんは、ものすごいスピードで成長しています。
もちろん、脳ミソもそうです。
ですので、他の年代の学習よりも、
“脳の発達段階に合った”学習を意識することが、とても重要になります。
そこで、まずは脳のしくみを簡単に理解するところから
お話をスタートしたいと思います。
どのような状態で小学校入学を迎えられるかは、
100%親御さんの責任です。
これは単に学力だけの問題ではありません。
長く将来までの、お子さんの人格形成に
とてつもなく大きな影響を与える問題です。
過剰な教育は逆効果ですが、出来る限りの準備を整えて、
小学校へ送り出してあげたいですね。
『1年生になる前に準備したいこと』 ~「はじめに」より~
2013年02月25日
“大好き”に巻き込もう

以前の投稿で、中学国語の教科書を眺めていて思ったことを書きましたが、
今回は、英語の教科書を眺めていて思ったことをお伝えします。
これも去年、千葉県で採用されていた教科書の話ですが、
中3英語教科書のレッスン1は、川平慈英氏のインタビュー記事が題材でした。
サッカーについて熱く語るという、氏ほどの適任者はいないだろうという内容です。
ところで、川平慈英をご存知ない方は少ないと思いますが、
簡単に氏のプロフィールを紹介します。
氏が世に出たのは上智大学在学中で、ミュージカル俳優として デビューされました。
その後、Jリーグの開幕に合わせ、
テレ朝のニュースステーションが募集したサッカーキャスターのオーディションに応募し、
日米(大学 時代にサッカー留学)での選手経験などが評価されて合格。
サッカーへの熱情にあふれた語り口で人気者となり、
日本サッカーの人気拡大に多大な貢献をされています。
世の中に認知されている氏のイメージと言えば、
“サッカー大好き兄ちゃん”といったところでしょうか。
そして、このことが、氏を 誰もが知るスターたらしめていることは間違いありません。
サッカー関係以外にも、舞台、映画、ラジオなど、多方面でご活躍ですが、
もし“サッカー大好き兄 ちゃん”でなければ、
中学の教科書にインタビュー記事が掲載されることはなかったのではないでしょうか。
つまり何が言いたいかというと、
何かが大好きであるという“自分が憧れている姿”を見せるだけで、
人を惹きつける魅力になるのだな、ということです。
学習塾時代には、講師にも、
“自分が憧れている姿”を生徒に見せるように、とアドバイスしていました。
「数学ってこんなに面白いんだぜ!」
「国語はこんなにスゴイのよ!」
という、講師自身が対象に魅力を感じている姿を見せて、
それに生徒を巻き込んでしまおう、 というのが狙いです。
勉強に限らず、どんな対象であっても良いと思っています。
最終的に、生徒が自分自身で大好きな何かを見つける力を身に付け、
「人生っ てこんなに楽しいんだ!」と感じてくれたら最高です。
そのためには、講師自身が、いろいろなことに興味を持ち、
学び続けていくという姿勢が必要になりますので楽ではありません。
が、だからこそ楽しい仕事なのだと考えています。
ということで今回は、ご家庭でも、
ご父母の皆様が大好きなものに“憧れている姿”を、
お子さんに見せたり、話したりされることをゴテイアンいたします。
お子さんが感化される程の迫力があれば、
“憧れ力”という素晴らしい力をプレゼント出来たことになります。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月23日
弱者の理論

さてさて、今回も少し、私の趣味の話にお付き合い下さい。
当ブログでもお伝えしましたが、私は小学校からサッカー部に所属し、
今でも草サッカーでボールを蹴っているサッカー小僧です。
日本サッカー界は、前回のW杯でベスト16という結果を残し、
ザッケローニという代表監督を迎え、来年のW杯本大会に向け、
予選突破まであと一歩というところにいます。
日本の報道ではあまりクローズアップされませんが、
監督の持つサッカー哲学、スタイルというものは、
サッカーというスポーツを楽しむ上で最重要な要素になります。
かなり大雑把に2つにカテゴライズすると、
「弱者の理論」基づいているか、「強者の理論」に基づいているか、
そういう分け方ができます。
今の日本が、世界をアッと言わせるサッカーをしたいのなら、
そこに必要なのは、「弱者の論理」に基づくサッカーです。
これは、私好みのスタイルでもあるのですが、
「自分より強い相手をいかにして倒すか」というところに知恵を絞るのが魅力です。
蛇足ながら、前回のW杯の時、直前まで“岡田ジャパン”は、
「強者の論理」でサッカーをしていました。
「自分たちのやり方を貫いて迎え撃つ」というスタイルです。
アジ アの強者である驕りが、
世界では弱者であると認めることを拒否していました。
テストマッチを負け続きで迎えた本番で急遽、
岡田監督は「弱者の論理」を用いた戦術に変えま した。
その勇気がベスト16という好結果をもたらしたと言えますが、
その勇気をもっと早く出していたら、と思わずにはいられません。
「横綱相撲」という言葉もあるように、
「強者の論理」にもそれなりの魅力はあります。
ただ、この話を自分自身のことに置き換えて考えたとき、
自分を成長させてくれるのは、やはり「弱者の論理」です。
なぜなら、自分の成長を考えたとき、敵は自分自身だからです。
“将来なりたい自分”が強者、“今の自分”が弱者です。
ならば「弱者の論理」で、「いかにして将来なりたい自分に近づくか」
というチャレンジを続けていかなければなりません。
そのためにはまず、“将来なりたい自分”を高く掲げることが必要です。
そして、“今の自分”が弱者であると認めることです。
相手が強ければ強いほど、知恵を振り絞らなければなりませんが、
そのことを楽しめるようになれば、何も言うことはありません。
素晴らしい人生のパスポートを手に入れたことになります。
いい意味での「弱者のメンタリティー」とは何か、
そのメンタリティーはお子さんの中に育っているか、
ご家庭で話題にしていただくことをゴテイアンいたします。
ちなみに、現在サッカーで世界一の監督といわれるモウリーニョは、
強者なのに弱者を装うことが出来るというスタイルなので最強です。
彼が世界一と呼ばれる所以ですね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月22日
パパは永年育児休暇中。

当ブログをお読みいただいている皆さま、
改めまして、どうもありがとうございます。
当ブログのコンセプトにつきましては、
初投稿でお伝えした通りなのですが、
このブログ以外にも、『パパは永年育児休暇中。』
というメールマガジンを発行しております。
私は、育児・教育関係のメルマガを100誌以上チェックしたり、
関連書籍を随時チェックしたりなど、情報収集と学習をしつつ、
連れ合いと共に、2児の子育て実践真っ最中です。
こうした実生活での経験や、収集した情報を元に、
育児に役立つアイテムやツール、ノウハウなどを、
定期的にお届けしております。
もちろん登録は無料ですので、
是非、メルマガにもご登録いただき、
ご意見やご感想などいただけると大変嬉しいです。
『パパは永年育児休暇中。』
ご登録はコチラ ⇒ http://yohei.biz/t/register
今回は、ちょっとご案内でした。また次回もお付き合い下さい。
2013年02月21日
テレビとの関わり方
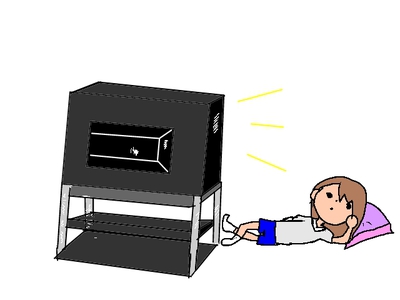
前々回のブログでも書いた通り、仕事柄、
読書の重要性は嫌と言うほど感じています。
ですので、自分の子は何とか本好きにしたいという目論見があるのですが、
そのマル秘作戦のひとつが、“面出し本棚”です。
娘が1歳の誕生日を迎えた時に、祖父母が、
誕生日プレゼントをリクエストして良い、と言ってくれたので、
遠慮なく『面出し本棚』を買ってもらいまし た。
聞き慣れない方もいらっしゃると思いますが、
よくどこかの待合室やロビーなどにある、表紙が見えるように本を並べられる、
こんな↓本棚です。
http://yohei.biz/t/hondana (ウチにあるものとは違うタイプですが…)
今のところ、その策略にまんまとハマッてくれていて、
ウチにこの本棚が来て以来、隙あらば本棚からお気に入りの絵本を取り出してきて、
読め読めと飽きずに催促してきました。
3歳になった今でも、本の読み聞かせは大好きで、毎日の日課ですし、
最近では、弟に読み聞かせをしてくれています。
10カ月の息子も感化されていて、
絵本を読み聞かせているときは、静かに集中して聞いています。
家の中にあると、大人が見てもなかなか良いもので、
自分にもひとつ欲しいと思った程です。
ただし、私の狭い家の中には無理なので、しばらくは我慢なのですが、
一家にひとつ、広いお家にお住まいの方は一人にひとつ、オススメです。
それで、話はまだ続きます。
本棚を買ってもらって少し経ったころ、
何かの情報が知りたくてテレビをつけっぱなしにしていたことがあったのですが、
あれだけ本に夢中になっていた娘が、テレビ画面に釘付けになっていたのです。
私もテレビは良く見ますし、テレビから学ぶことも多いので、
闇雲にテレビはダメだという意見には反対なのですが、
それにしてもその圧倒的な刺激は恐るべきものだと感じました。
という訳でテレビは、視聴時間や見る番組の質など、
子供を持つ親としては気を付けてあげなければならないな、と思った次第です。
ちなみに、日本の子供のテレビ平均視聴時間は2.7時間で、
国際平均の1.7時間より1時間も長いそうです。
また、宿題をする時間は1.0時間で、国際平均の1.7時間よりも0.7時間少ない
というデータも出ているようです。
日本の国際競争力低下や学力低下が叫ばれて久しいですが、
そのことの一因が垣間見えます。
ご家庭でも、テレビとの関わり方について、
改めて親子で話し合いをする機会を持たれることを強くゴテイアン致します。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月19日
学びのきっかけ

オスプレイ、普天間、TPP、拉致、尖閣、竹島、北方領土・・・・・
ちょっと考えただけでも、日本の外交は多くの問題を抱えています。
そして、どれをとってみても、
日本政府の対応はあまりにも稚拙で、ちゃんと勝算、戦略があるのかよと
思わず突っ込みを入れたくなることばかりです。
ただ、このブログは時事問題を扱う趣旨で はありませんので、
話を深めず、子供のことに視点を移したいと思います。
事あるごとに日本は近隣諸国との軋轢が表面化しますが、
その時こそ、日本の歴史を学ぶ絶好のチャンスです。
なぜ今このような問題が起きているのかを知るためには、
歴史を知らなければなりません。
池上さんの ニュース解説が人気であることからも分かるように、
ニュースの真相に迫るという行為はとても面白いので、
歴史への興味が湧きやすいのです。
この地球上の出来事と自分は無関係ではない、
そう考えられる子どもを育てたいと思っています。
さらに言えば、歴史という大地の上に立って現状を考えることが出来るか、
これは本当に大切な能力です。
過去を知り、反省し、明るい未来を築いていく能力です。
ただし、ニュースで報道されているような出来事は、
子供にとってはハードルが高すぎますので、手ほどきは必要です。
私も授業で、必然的に社会の授業時が多くなりますが、
時事問題から歴史を紐解いて話すことがあります。
私はそれが仕事ですが、ご父母がいつもお子さんにニュース解説する
という訳にもいかないと思われますので、
今回は、お子さんが自分で手軽に歴史を学べる方法をお伝えします。
その方法とは、『マンガ日本の歴史』を読むことです。
絵によるイメージも加えて学べるので、
文字だけよりの教科書よりもずっと頭に入りやすいです。
中古で購入すれば、全巻集めてもそこまで高価ではありませんし、
値段を上回る価値があると思います。
何社かから出版されていますので、お好みでお選び下さい。
学習まんが少年少女日本の歴史 ⇒ http://yohei.biz/t/rekishi
僭越ながら、ご父母の皆様には、同じ昭和生まれとして、こちらをオススメします。
私たちは自覚を持って伝えていく義務があると思うのです。
もちろん、お子さんにも読ませてみて欲しいと思います。
コミック昭和史 ⇒ http://yohei.biz/t/showa
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月18日
もっと語彙力を

中学校の定期テスト対策を考える時など、改めて教科書を眺めることがあります。
お子さんの教科書の内容を見ておくことは、必要な事でもありますし、
結構楽しいと思うので、ご父母の皆さんにもオススメです。
これは千葉県で採用されていた国語の教科書の話ですが、
各学年とも最初のページに、加藤周一氏のコラムがあり、
その後に、「身につけたい言葉の力」というものが定義されていました。
〔想像する力/批評する力/情報を収集する力/論理的に思考する力/対話する力/伝統を受け継ぐ力〕
これが、文科省が義務教育終了時に身につけさせたいと考えている言葉の力です。
学校では、そのための授業が行われていますが、
当然それだけでは不十分で、自助努力が必要です。
そこで今回は、具体的にどんな努力をしていけば良いのか考えてみます。
上記の力をより効果的に身に付けていくためには、語彙力を増やしていくことです。
もっと「言葉を持つ」ということです。
言葉を多く持つことで、自分で思考す るレベル、相手に伝えるレベル、
相手から受け取るレベルが飛躍的にアップします。
そのことが、どれほど人生を豊かにするかは言うまでもありません。
次に、どうやって語彙力を増やしていくかですが、残念ながら特効薬はありません。
ただ、基本的には書物に触れることが一番だと思います。
人と直接コミュニ ケーションをとることはもちろん大切ですが、
日常で接する人物は意外に限られていて、
これまで持っている言葉だけで事足りてしまう場合が多いので、要注意です。
家庭教師では、語彙力を増やしていくための方法を、個別にアドバイスしています。
内容は個人によって変わりますが、共通し ているのは、
「習慣化」することが最も大切だということです。
今だけ、テストのため、ということではなく、ずっと学び続けるのだという意欲が大切です。
そこで今回は、まずご父母の皆さんが、
ご自身の語彙力をさらに増やしていくための工夫を実行して、
そのノウハウをお子さんに伝授していただくことをゴテイアンします。
現在のご自身の語彙力を推定してくれるサイトをご紹介しますので、お役立て下さい。
お子さんの語彙力チェックにもお使いいただけます。
語彙力推定テスト ⇒ http://yohei.biz/t/goiryoku
(携帯電話だと操作が困難なものもあるようです。)
最後にひとつ、すぐに出来る具体策をゴテイアンします。
それは、何事に付けても「すごい!」「微妙…」という感想を言わないようにすることです。
この2つの フレーズだけで済まされてしまっていることが多すぎます。
試しに、お子さんに何かの感想を聞いてみて下さい。
高確率でこのフレーズが出てくるはずですが、だとしたら要注意信号です。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月17日
勉強の仕方が分からない

今回は、面談時などにもよくお受けする
「勉強の仕方が分からない」という質問について、
いくつかのチェックポイントをお伝えします。
まず、勉強の仕方が全く分からないのかどうかを確認します。
例えば英語なら、
「英語が出来るようになるために、どんなことをしたらいいと思う?」
と聞いてみます。
考えることを放棄していない限り、
「単語を覚える」とか「ワークを繰り返しやる」程度の答えは返ってきます。
次に、そのことにどれだけ時間を使ったかを確認します。
さっきの例ならば、
「単語の練習を~日間に~回、~時間、どれくらいの期間続けてやったか」
を聞いて みます。
この時点で、学習時間が絶対的に不足していることに気付く場合が多いです。
3日坊主ならまだ良いほうで、1回試しただけ、
ひどい場合は頭の中で シュミレーションしただけ、という場合も少なくありません。
単語の例で言えば、苦手としているなら最低1日15分、毎日、1ヶ月は続けてみて、
それでも成果が出ないということであれば方法の再検討に値しますが、
そうでなければ検討する以前の問題です。
も し、上記2つのステップをクリアーしている場合は、
やっと勉強内容の改善点を確認をする段階です。
ただ、1ヶ月続けていれば、
自分なりの改善方法が見えて くる場合がほとんどなので、
今度はそれを試していくことになります。
また、1ヶ月続けても成果が出ない場合、方法よりも気持ちの問題で、
「ただ教材を眺め ていただけ」だったり「機械的に書き取りをしていただけ」
だったりが原因であることも多いです。
その場合は、気持ちをセットし直さなければいけません。
「勉強方法が分からない」と言っている子に限って、
教材からやり方まですべて伝えても、
宿題をやって来ない子が多いのも事実です。
この場合、やりたくない言い訳 として「勉強方法が…」と言っているだけ、
または「“努力しないで成績が上がる”勉強方法が分からない」と言っているということです。
そんな夢のような方 法があれば喜んで教えますが、さすがに無理な相談です。
以上になりますが、状況はお子さんによって個別具体的ですので、
いつでもご相談下さい。
出来ればその前に、今回お伝えしたチェックポイントを、
お子さんと確認されることをゴテイアンいたします。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月16日
勉強の前に気を付けること

もう2月も中旬を過ぎましたね。
中高生は、受験や定期テストなど、一年で一番危機感を持って勉強する期間かも知れません。
普段の学習習慣が付いているか否かに関わらず、
机に向かう時間が長くなる時期とも言えますが、
せっかく机に向かっても、ただボーッと過ごしてしまっては意味がありません。
今回は、そうならないために、
まず勉強を始める前に気をつけるべきことを3点、お伝えします。
1つ目は、おなかをすかした状態は避けよう、ということです。
脳の細胞は、ブドウ糖と酸素だけをエネルギーとして使い、
これがないと活発に活動しません。
ですので、しっかりゴハンを食べ、消化を助けるために30分休憩して、
勉強を始めるようにしましょう。
2つ目は、集中できる環境をつくろう、ということです。
テレビやラジオをつけながらだと、脳の多くの場所が働いてしまい、
集中が出来ません。
また、明日の準備など、ほかに気になることがあれば、先に片付け、
安心した気持ちで勉強することも大切です。
3つ目は、よく眠るようにしよう、ということです。
「眠いな」と感じた時、脳はつかれています。
十分に寝て疲れを取らないと、脳は活発に働きませんので、気をつけましょう。
スポーツでは、試合に臨むためにコンディションを整えるのは常識ですが、
それは勉強にも当てはまります。
学校や塾、自主学習に臨むコンディションについて、
改めて見直しをされることをゴテイアンいたします。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月15日
親力で決まる子供の将来
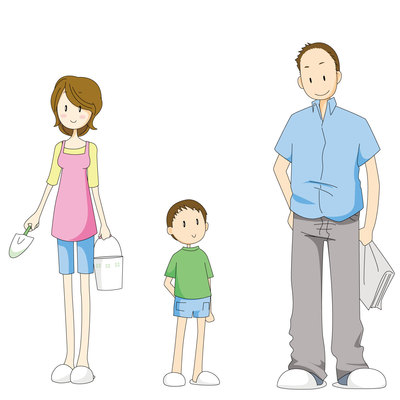
情報化時代と言われて久しいですが、今の時代は本当に便利になり、
インターネットを上手に活用すれば、
いつでも最新の情報や、有益な情報を揃えておくことができます。
ということで今回は、私がチェックしているブログやメルマガの一つをお伝えしようと思います。
このブログの趣旨に沿い、カテゴリーは教育・学習です。
私はこれを生業としてきましたし、今でも家庭教師を受け持っておりますので、
関連の著名人や有識者、その他気になる人のブログやメルマガ、
‘Facebook’‘Twitter’などのソーシャルネットワークサービス(SNS)は随時チェックしています。
その道の権威である方の意見や、専門家による何十年という研究の成果などが、
惜しげもなく、すぐに手の届くところに公開されているというのが今という時代です。
これを活用しない手はありあません。
今回紹介するのは、教育界№1の発行部数を誇る、現役小学校教師のメルマガです。
親野智可等(おやのちから)というペンネームの発行人は、現役教師を続けながら、
子供に対する親の影響力の絶大さを日々、思い知らされた(私も激しく同意)と言います。
そして、こう言います。
「親たちが自分たちなりに精一杯やっていることは知っています。
ただ同時に、気持ちはあっても具体的にどうしたらいいのか分からない、
ちょっとしたコツが分からないで見当違いのことをし、
逆効果になっていることが多いということも知っています。」
それを助けたい、サポートさせて欲しい、という想いからスタートしたのだ、
というメルマガです。
発行人は小学校教師ですので、小学生のご父母はもちろんですが、
中学生のご父母にも十分参考になる内容です。
直接当てはまらないケースも、
これまでにそうしてこなかったことが現状の原因なのかもと推測して、
今後の対応を考えることが出来ます。
無料ですのでよかったら登録してみることをゴテイアン致します。
下記のアドレスから入り、「登録」ボタンをクリックするとメール送信画面が開きますので、
何も入力せずそのまま送信すると、登録完了のメールが届いて登録完了となり、
後は随時、メルマガが送られてきます。
『親力で決まる子供の将来』
(PC版)http://yohei.biz/t/oyaryoku-p
(携帯版)http://yohei.biz/t/oyaryoku-m
それでは、今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月14日
レベルアップのためには

さて今回は、ちょっと私の好きなサッカーの話にお付き合いいただこうと思います。
私は小学校からずっとサッカー部に所属し、
少なくとも平均値以上はサッカーを知っていると自負しておりますが、
日本サッカーのレベルは、完全に停滞しています。
マスコミはいつも「過去最強」とはやし立てますが、
スポーツというものの性質上、過去よりもレベルが上がるのは当然です。
問題は、周りの世界と比べた時にどれだけ進歩したかですが、
日本のレベルは、贔屓目に見ても、停滞しています。
今度のW杯の出場は、アジア枠がゆるゆるなので確実でしょうが、
本大会では、前回のような成績を残すことは、今のままでは無理です。
もちろん、そうならなければ一番いいのですが、ある意味では惨敗を望んでもいます。
それは、日本サッカーにもっと強くなって欲しいと心から願っているからです。
どういうことかと言うと、日本サッカー協会やマスコミ、
及び日本のサッカーファンは、振り返りと反省をしません。
日本のレベルを何とか引き上げようとしているのは、選手たち本人だけ。
これでは強くなりません。
この当たり前のメカニズムに気付いてもらうためには、
強烈な刺激を受けるしかないのかも知れません。
日本サッカー協会の予算は200億に迫ると言われ、
恐らくダントツの世界一です。
サッカーは野球に次ぐ人気スポーツで、プロリーグもある。
それだけ見れば、前回のW杯で岡田監督の言った「ベスト4」は
妥当といえる程の環境なのです。足りないのは、反省と自己変革です。
これが出来ないから、また負けるのです。
ここまで書いてくると、お子さんのことが重なってくるご父母もいらっしゃるでしょう。
そうなのです。まったく一緒なのです。
勉強が出来るようにならない子が、勉強できるようにならない理由と、
日本サッカーが強くならない理由は、まったく一緒なのです。
振り返り、反省し、良かった点と悪かった点を分析し、
現実的に次の目標を立て、それとのギャップを把握し、
どうやってそのギャップを埋めていくかを考え、
気持ちを変えて、行動を変えて、自分を変えていく。
その先に初めて、進歩があるのです。
今や日本代表の中心選手となった本田圭佑は、こう言いました。
「オランダの2部で目立つためには作っていてはダメ。
ゴールを奪わないと誰も注目してくれない。
そのためには、いままでの自分を全て否定することから始めた」
成績を上げていくには、いままでの自分を全否定するくらいの姿勢が必要です。
学習塾時代には、テストが終了した生徒に対して、
振り返りをする機会を必ず持つように講師に指示を出していました。
進歩するためには反省が必要だということが分かり、
その習慣が身につけば、テストの成績のみならず、
どんな壁も乗り越えられる力が手に入ります。
それまでを全力でサポートさせていただくのが講師の役目と伝えてきました。
現在、私が家庭教師をさせていただいている生徒にも、
もちろん同様に伝えていくつもりです。
という訳で今後、サッカーは試合後の動きにまで注目して、
反省と進歩の関係を客観的に見ていただき、
お子さんへの戒めとしていただくことをゴテイアンいたします。
それでは、今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月13日
いつもフレッシュでいたい

私には子どもが2人おります。
娘は3歳、来年度から保育園に入園出来れば社会デビューです。
息子は10カ月。最近、歯が生え始めたので、次の目標はあんよですね。
今回は、自分の子どもたちを見て思ったことの一つをお伝えします。
それは、
「子供の小さな変化を見逃さず、タイミング良く褒めてやる」
という心構えを、いつまでも忘れないようにしたい、
ということです。
ご経験から実感していただけることと思いますが、赤ん坊の頃は、
笑った、声を発した、ミルクをたくさん飲んだ、寝返りを打った、パパママと言った・・・・
などの本当に些細なことで、親というものは一喜一憂します。
それが小学生、中学生・・・と成長していくうちに、
知らず知らずのうちに期待のレベルが上がってしまいます。
ここで問題なのは、
赤ん坊の頃よりも明らかに見ている時間は少なくなっているのに、
要求のレベルだけは上がっているということです。
成長と伴に、超えるべきハードルの高さは上がっていきますので、
期待値も上がっていくのは当然です。
叱ったり、お説教しなければいけない機会も多くなっていくでしょう。
それは必要なことだと思います。
ただ、時間的には赤ん坊の頃とまではいかなくとも、
その頃と同じような気持ちで子供の成長を見ていこう、とすることで、
赤ん坊の頃と同じように褒めたり、認めてあげたり、
小さな変化に気付いてあげることが出来れば、
それはとても素晴らしいことだとも思います。
もちろん私の場合は職業として子どもを見てきたので、
生徒に対しては、そうした視点を忘れることはありません。
ただし、我が子となれば話は違ってきます。
いつも一緒にいる分、いろいろな部分が目につくし、
可愛い分、その期待が過度に膨れてしまう危険も大いにあるからです。
その対策としては、出来るだけ多くの意見に耳を傾け、
出来るだけ客観的に状況を把握していこうという努力をすることだと考えています。
ですので、保護者面談の時などに、親業の先輩として
ご父母の皆さんにお話を聞かせていただくこともあったりする訳です。
当ブログでも、皆さんからのアドバイスがいただけると大変嬉しいです。
話が少し飛躍しましたが、とにかく今回お伝えしたいポイントは、
「お子さんが初めて○○した時の感動を思い出し、
その時と同じ気持ちで現在のお子さんを見てみると、
新しい発見があるかも知れませんよ」
ということです。
今晩は、お子さんの産まれた日のことなどを、
ご家族でお話しになってみることをゴテイアン致します。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月12日
ケアレスミスをなくすには

世間は連休でも、受験生にとっては入試シーズン真っただ中ですね。
受験本番では、何より自分の力を100%出し切ること、これに尽きます。
と言うことで、今回のテーマは『ケアレスミス』です。
まずその意味を定義しておきたいと思います。
私が言う『ケアレスミス』とは、『“その人にとって”簡単な問題を間違えること』です。
簡単か難しいかというのは、完全に主観的な判断ですので、客観的に見て、
「君の能力から考えると、この問題は絶対出来たはずだし、この前は出来てたじゃん!」
というミスを、『ケアレスミス』と定義することにします。
そう定義してみると、原因がだいぶスッキリ見えてきます。
問題が“その人にとって”簡単なレベルであるならば、つまり、頭は足りているということになります。
となれば、足りないのは結局、気持ち以外にはありません。ハートです。
なんだ、あたりまえのこと、と思った方もいらっしゃるでしょうが、やっぱり“気合い”は大事です。
「絶対全問正解してやる!」 「次は絶対間違えないぞ!」 「出来るようになってやる!」
という気持ちで、魂を込めて問題に取り組んでいるかとうかです。
ただ参考書を広げていても、ただ何百題の問題を解いても、
気合いがなければ成績は絶対上がりません。
あたりまえのことですが、もう一度このことの重要性を本気で考え、自問自答することが必要です。
もうひとつの原因、これは意外と盲点かも知れませんが、“生活習慣”です。
朝、自分で起きてますか?
遅刻はありませんか?
忘れ物はないですか?
宿題は、きちんとやっていますか?
人との約束、守れてますか?
自分との約束、守れてますか?
「まあいいや」という気持ちで日々ダラダラ過ごしていて、
テストの時だけはシャキッとミスが無い、という人がいるでしょうか。いませんよね。
いてもマグレ。ここ一番にマグレを期待してはいけません。
テストの答案には、それまでの生活習慣も全て出てしまうものなのです。
ここ一番の勝負の時、いつもとは違う精神状態の時、それが顔を出すのです。
悪い習慣からは、悪い成績が。
良い習慣からは、良い成績が。
これまた至極当たり前の帰結です。
どうしてもケアレスミスが無くならないという人は、まず生活習慣を見直すことをオススメします。
なお、そのためには、まず自問自答することが大切ですが、
次に、生活を一番身近で見てくれている家族に意見を求め、
素直に受け入れることが出来るかがポイントです。
シーズン真っただ中の受験生でも、今からやるしかありません。
遅いも早いもない、もう今になってしまったので、今からでも立て直しましょう。
受験生も、その他の学年も、これを機に、
ケアレスミスを減らすためにはどのような姿勢で取り組むべきか、
家族が出来るサポートは何か、ということを話し合われることをゴテイアンいたします。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月10日
1対2のマッチング
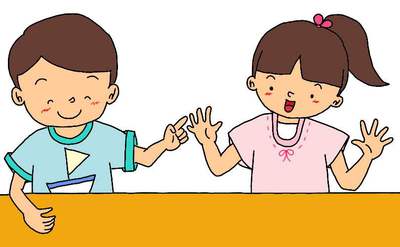
当ブログでもご案内しております通り、現在、
組数を限定して、家庭教師のご依頼を募集しております。
(1対2:14,700円/月 1対1:18,900円/月)
「1対2で申込みたいけれども、相手が見つからない」
という方には、こちらでマッチングさせていただくことも可能です。
家庭教師は1対1が基本かと思われますが、
個別指導塾で行ってきた1対2指導のノウハウで、
1対2の授業も行っております。
机を並べて勉強する相手がいると、相乗効果を発揮できるケースが多々あります。
ご兄弟やお友達と一緒にお申込下さい。
もちろん、ご希望に合わせて、1対1の指導も可能です。
マッチングをご希望の場合は、他にも希望者がいらっしゃることと、
両者の間で、教場をどちらにするか、曜日や時間帯は合わせられるか、
などの折り合いがつけられれば、という条件付きにはなります。
まずは、当方まで、「マッチング希望」の旨、ご連絡下さい。
マッチング成立までお待ちいただくか、
1対1でスタートして、成立次第1対2に移行していただくか、
どちらも可能ですので、ご相談下さい。
2013年02月09日
競争意識を持たせるとは

さて、今日お伝えするのは『競争意識』についてです。
大半のご父母は、お子さんに(特に勉強に関して)競争意識がないことをお悩みです。
そして、
「競争意識を持たせたいから集団塾で」、「マイペースな性格だから個別塾か家庭教師で」
といった判断基準を持っている方が多くいらっしゃいます。
自分が個別指導をやってきたから言う訳ではありませんが、
後者はともかく前者については、ちょっと待ってくださいよと、思わず言いたくなってしまいます。
本当の競争意識とは誰に対して持つものかと言えば、
“昨日の自分”に対してです。
勝負は、子供にそのことを気付かせられるかどうかです。
子供が、昨日の自分を越えることに価値を見出してくれるように、
成長している姿をしっかりと見つめ、タイムリーに認めてあげ、
それを上手に伝えてあげることが必要になります。
それと、集団の中にいれば競争意識が芽生えるというものでもありません。
ただ、周りの意識に感化されるということは大いにあると思います。
ここで勘違いしてはいけないのが、集団塾と個別塾、家庭教師の違いは、
あくまでも授業の形態の違いだということです。
集団塾だから人がたくさんいて、個別塾や家庭教師だと
周りの子を意識しないという訳では全くありません。
集団塾でも個別塾でも生徒はたくさんいますし、
家庭教師だって、授業の時に1人なだけであって、
彼らの日常なのかには、周りに手本となるような生徒が必ずいます。
大事なポイントは、子供自身のアンテナが、そのことを、
自分を奮い立たせる情報としてキャッチできる感度を持っているかどうかです。
それがなければ、周りがどんな環境でも、一切関係ないのです。
ご家庭でも、お子さんが自分の成長を楽しんでいるかどうかを観察し、
感度の良いアンテナに磨き上げていくための施策をとられることを強くゴテイアンいたします。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月08日
“ゆとり”と言われる若者たち

子どもが産まれてからというもの、めっきりテレビを見ることが少なくなり、
奄美移住後に至っては、家にテレビがない生活を送っています。
ただまあ、質の高いテレビ番組は積極的に見た方がいいという考えなので、
このブログでも、テレビの話題に触れることはあると思います。
今回は、「“ゆとり”と言われる若者たち」という番組を見て考えたことをお伝えします。
週5日制、総合学習といった大幅なカリキュラムの変更が始まったのが1992年。
当時小学1年生として入学した世代が今年、社会人3年目です。
社会人3年目といえば、新卒採用者の3人に1人以上が離職するのが昨今です。
この世代は、小学6年生の時代にインターネット普及率が50%、
高校1年生の時代には60%を超えるなど、
情報インフラの発達とともに育った世代とも言えます。
番組では、この「ゆとり世代」と言われる世代の特徴を、
①浅いコミュニケーション
②失敗を極端に恐れる
③言われたことしか出来ない。
と、まとめていました。
①について、
携帯メールで育った彼らにとって、メールは無くてはならない手段です。
電話は、かけるタイミングによっては相手に迷惑になって嫌われてしまうかも知れないので、
あえて無難なメールでコミュニケーションを取ってしまおうと考えます。
気持ちは分からないではありませんが、
「相手を思いやる気持ち」こそがコミュニケーションの真髄です。
伝達手段が増える一方で、意思疎通の程度が浅くなっているという指摘には、
なるほどと納得してしまいます。
②、③のポイントも的を射ていると思います。
特に、お勤め先で、新入社員を教育された経験のある方は、実感されていることでしょう。
企業の新人教育も紹介していましが、「褒めて育てる」という視点から、
徐々に「叱って育てる」という視点を重視しているそうです。
学校や家庭で叱られることに慣れていないこの世代は、上司に怒られると、
自分を理解してくれていないとして会社を辞めてしまいます。
これらのことは、社会に送り出す側の仕事をしてきた私としては、
ものすごく実感できる現象であると同時に、ものすごく大きな責任を感じている次第です。
私が申し上げたいのは、「“ゆとり世代”はダメですよ」ということではありません。
ただ言えるのは、「ゆとり」と呼ばれる世代があって、少なくとも彼らの周りには、
以上のような「ゆとり」の負の特徴を持った仲間が多くいるということです。
それと、もうひとつ。
悪いのは子供ではなく、こうした状態を生み出してしまった大人だということです。
それは、教育を職業としている私はもちろん、
この文章を読んでくださっている全ての大人の方々も、無関係ではあり得ません。
この2つのことは、しっかりと自覚しておかれることをゴテイアンいたします。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月06日
受験という壁の越え方
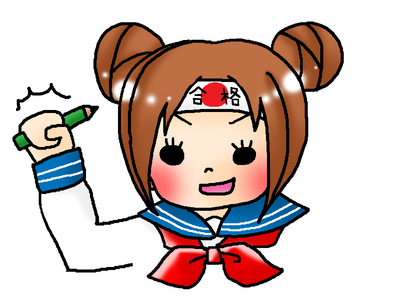
いよいよ、受験の季節がやってきました。
現在、組数を限定して家庭教師の募集をしていますが、
今のところ受験生は担当していないので、
去年までの学習塾時代を、少し懐かしく思っています。
受験に対する心構えとして私が生徒に話していることは、
「壁を乗り越える自分のスタイルを築け」
ということです。
これは、「人生の勝ちパターンを身に付けろ」と言っているのと同じです。
人生には、様々な壁があります。
それを、どのように乗り越えていくか、または避けて通るのか、
その人間の人生の価値が決まる場面です。
目標を睨みつけて全力で立ち向かうか、
回避できる方法を探して妥協するか、
人生の選択は、いつでも自由。どちらも正解です。
しかし、どの道を選ぶかは、人生の価値を大きく変えていきます。
今大事なのは、“前のめり”で次の段階にに行けるかどうかです。
前のめりに壁を乗り越えた時、
それが生徒たちにとって、どれほど人生の財産になるか、と思っています。
“前のめり”でありさえすれば、合格・不合格を問わず、
次の場所で、充実した生活を送る最高のアイテムを手に入れたことになります。
そして、ここで身に付けたスタイルというものが、少なからず、
今後の人生で壁を乗り越える時の基本スタイルになります。
「ここで頑張れない奴は、一生頑張れない。」と、生徒に言っています。
受験校は関係ありません。ランクを下げて受けるなら、トップ合格を目指すまでです。
しかしながら、渦中の子供本人は、
自らそこまで考えられるケースの方が少ないです。
だからこそ、サポートする周りの大人たちが、
子供の人生を大きな視点で捉え、導いてあげることが重要です。
どうしたら受験を通して、人生を幸せに歩む力の基本を身に付けさせてあげられるかが、
最大のテーマになります。
受験生以外は定期テストがありますが、これこそ壁を乗り越える恰好の練習です。
ここでしっかりと練習を重ねた者にのみ、
受験で魅力的なチャレンジが出来る権利が与えられます。
ご家庭でも、「壁の乗り越え方」について、
まずはご父兄自身のご経験をお子様にお話して、
話し合う機会を持たれることをゴテイアンいたします。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2013年02月05日
聞くよりも聴く

前回のブログで、コミュニケーション能力が大事だとお伝えしましたが、
それはもちろん、リードする側の大人にも必要な能力です。
今回は、私が生徒とコミュニケーションをとる時に心がけていることをお伝えしようと思います。
それは、「こちらの考えを伝える前に、まず相手を理解するための努力をする」ということです。
これは一見、簡単なように見えて、実は、常に意識していないと実行するのが難しい姿勢です。
なぜなら、子供というのは、大人よりも経験値が低いことが多いため、
大人から見るとどうしても思慮が浅いと感じてしまい、
上から目線で説教をしたくなってしまうからです。
また、ボキャブラリー(語彙力)も少ないため、
心の内面を適切に表現出来る能力が身に付いていないので、
大人から見るとどうしても物足りなく感じてしまい、
上から目線で説教したくなってしまうからです。
ですので、そんな時は自分の心の『一時停止ボタン』を押して、
子供の表情をしっかりと見て、表現できていない心の中を読み取るように努めています。
場合によっては、読み取ることが出来るまでに時間がかかることもありますが、
そこはグッとこらえて、手を変え品を変え、さまざまな角度から話を聴いて、
本音を引き出せるように努めます。
どうしてそんな面倒なステップが必要かというと、
子供に限らず人間というものは、
「自分のことを理解してもらっている」と感じることが出来るまでは、
相手の話の内容など、どうでも良いことだからです。
だから今、『聞く』ではなくて『聴く』という言葉を使いました。
『聴く』という字は、『耳』と『目』と『心』が『十』あると書きます。
ご家庭でも、お子さんの話を、ただ『聞く』だけではなく、
『目』と『耳』と『心』を、今までの『十』倍使って『聴く』ことを強くゴテイアンいたします。
それでは、今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。