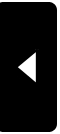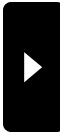2019年01月28日
小学英語をどうとらえるか
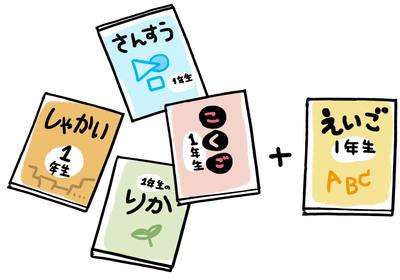
日本人が英語を習得するのに、
どれくらいの時間がかかると言われているかというと、
2400~3000時間です。
これに対して、日本の中・高で英語を勉強する時間は、
ざっくり1500時間くらいです。
そもそも、
英語を話さなくても済んでしまう環境で、
細切れの時間で学ぶというデメリットもあるので、
なかなか身に付かなくて当然なのですね。
そこに小学英語の時間がちろちろっと加わったところで、
ほとんど効果はないのではないかと思います。
学校の授業だけではもちろん、
週に1~2回の習いごとをした程度では、
英語を身に付けるのは無理な話だと思います。
決して習い事に意味がないと言っているのではありません。
小学校で英語の授業をするのも悪くないです。
ただし、英語がペラペラになりたい、という期待はせず、
中学英語の準備をするんだ、という意識で取り組むことです。
過度な期待は禁物ですし、
必要以上にあせって取り組む必要もないです。
新しい語学を学ぶということは、本来楽しいことですから、
子どもが楽しんで学ぶことが出来ていれば、
それで良しとするのがいいのではないでしょうか。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月27日
小学生の英語教育

文部科学省の方針で、小学校3年生から、
「外国語活動」が実施されていますね。
グローバルな時代を生き抜く人材を育てたい、
というようなことだと思うのですが、
英語を話せるようにしたいなら、
英語しか使えないような環境に放り込むのが一番です。
週に数時間、ちょろちょろっとやったところで、
話せるようには絶対ならないですね。
小学校で英語の授業を取り入れたからといって、
国際競争力のある人材が育つとは全く思えません。
それでも、学校では授業が行われるわけなので、
どうやって向き合っていけばよいのか、
ということは次回のテーマにさせて下さい。
今回お伝えしたいのは、この年代、
それより身に付けたい能力がもっとあるよねって話です。
全ての教科の土台になるのは、国語力です。
これは間違いない。
この時期にしっかり国語力をしっかり付けることが、
英語力や算数力の土台になります。
まずは国語力。そう思います。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月26日
目を見てあいさつを

小学生の子どもがおりますので、
はた振り当番で、朝の登校シーンを見る機会があります。
こちらはもちろん、
目を合わせて元気よく、にこやかにあいさつします。
反応は様々ですね。
元気よく目を合わせて返してくれる子、
目を伏せて無言で通り過ぎていく子、
恥ずかしそうにはにかんで返してくれる子、
お友達とのおしゃべりに夢中の子。
いろいろなタイプの子がいるのは大前提として、
それでもやっぱり、
目を合わせてあいさつ出来る子にはなって欲しいですよね。
陽平塾の塾生は、特に約束事を決めたわけではありませんが、
来塾時と帰る時、必ず目を見て、
「こんにちわ!」 「ありがとうございました!」
と言ってくれます。
とてもいい子たちです。みんなこうなって欲しいです。
気持ちの良いあいさつは、
人間関係、コミュニケーションのキホンのキですからね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月25日
「終わったら教えてね」が出来ない子

陽平塾にだけだとは思えないのですが、
「ここまで終わったら教えてねー」
と指示を出して問題を解かせたのに、
終わっても教えてくれないでボーっとしていたり、
自分で適当に他の問題を解いたりする子が多いです。
他の子に教えている最中だから気を使ってとか、
こちらが声をかけるタイミングを与えていないとか、
そういうことではなく、声がかけられないのです。
中には引っ込み思案で恥ずかしいのかな、
という子もいますので、もちろんそういう場合はフォローします。
ただ、そうでもないのにも声がかけられない子も多いので、
そういう問題でもなさそうなのです。
こちらは、
「ここまでの出来をみて、次の展開をかんがえよう」とか、
「ここをしっかり解説してから、応用問題にチャレンジさせよう」とか、
そういうプランを持って授業をしているので、
それが狂って、効率が悪くなってしまうのです。
それで、こうしたことを何度説明してもダメな子もいたりして、
けっこう困っています。
最近ではもう受け入れて、対策を取るようにしてはいます。
でも、このままこういう子たちが大人になった時、
仕事が終わっても上司に報告しないでボケっとしている、
何かミスをしたのに黙ったままでいて後で大問題になる、
みたいな社会人にならなったらと思うと。
社会人の基本は、報告・連絡・相談ですからね。
とても心配です。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月24日
「わかる」は「かわる」
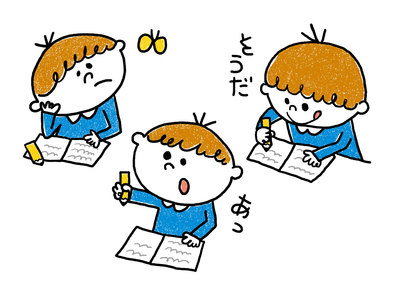
「わかった?」
「わかりました!」
というやりとり、いろいろなケースであります。
もちろん塾でも、
間違えた問題を説明をした時、
宿題をして来るよう行動の改善を促した時など、
色々な場面でするやりとりです。
でも、わかってないじゃん、という場合も多々あって、
そんな時はこう言うようにしています。
「わかる」ということは行動が「かわる」こと。
行動がかわっていないということは、わかってないんだよ。
どうですか。
使いたくなる場面がけっこう思い浮かんだのではないでしょうか。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月23日
受験生の母の心配事

今年もまたインフルエンザが流行っていますね。
受験生の母親を対象にしたある調査によると、
受験を控えた子どもに関して心配していることは、
「風邪やインフルエンザにかかること」(72.4%)
「体調管理」(65.6%)
「勉強・学業」(48.3%)
だそうです。
ですよね、それはそうです。
試験で最も大切なことは、普段の力が発揮できるかですからね。
風邪やインフルエンザは水際対策が大切ですので、
マスクをして、手洗いうがいをしっかりして、
あとは生活リズムを整えることです。よく寝ましょう。
受験生をお持ちの親御さんは、その点だけ注意してあげて下さい。
個人的には、予防策の決定版として、
クロレラ工業株式会社の「バイオリンクBCEx503」を飲んでいます。
奄美なら石橋町のムラタ薬局さんで扱っているので、
話を聞いてみるのもオススメですよ。
「ようへい先生のブログで見た」と言うと話が早いかもです。
分かりやすく説明してくれますよ。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月22日
理系の方が就職に有利?

今年度の大学生の就職内定率は、8年連続で上昇して、
過去最高の87.9%になったようです。
ここ数年、売り手市場が続いていますね。
地域別でみると、トップは関東地方の90.5%、
我らが九州地方は最下位の80.5%だそうです。
まあ、これはこれで何とかすべき問題ですが、
いつも気になるのは、
進学希望の高校生に文系理系選択の根拠を聞くと、
就職に有利だから理系、という子がとても多いことです。
いやもうそれ2昔前の話だから、という感じです。
実際、今回の調査でも、
文系87.7%、理系89.0%と、就職内定率はほとんど同じです。
だったら、
好きなこと学んで高校時代をもっとエンジョイしなよ、と思います。
結果その方が、
企業が求める人材に成長できる確率は上がると思いますよ。
就職どうこうとかちまちま考えず、
嫌いな教科より、好きな教科をもっと勉強しましょう。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月21日
正しいほめ方

子どもはほめて伸ばしましょう、とは
よく聞くフレーズだと思いますが、
何でもかんでもただほめれば良いという訳ではありません。
中室牧子さんの『「学力」の経済学』の中に、
正しいほめ方とも言うべき研究結果が紹介されています。
「子どもをほめるときは、何をほめるかが大事」だということです。
結論から言うと、才能より努力をほめるということです。
「頭がいいね」と能力をほめられた子は、
できた時もできなかった時も、才能のせいだと考える傾向があるそうです。
できなかった時は、「才能がないんだからしょうがないや」と。
これに対して、
「よく頑張ったね」と努力をほめられた子は、
できなかった時は、「努力が足りなかった」と考える傾向があるそうです。
ですので、
「具体的に努力した内容を取り上げてほめ、
さらなる努力を引き出し、
難しいことにも挑戦しようとさせるほめ方」
が大切だと紹介されています。
これ、正解ですよね。
みなさんも参考にされてはいかがでしょうか。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月20日
学年によって変わる雰囲気

何年も子どもたちを見てきて思うのが、
学年による雰囲気の違いってあるなー、ということです。
それによって各個人が受ける影響も、
少なからずありますよね。
まあ、お子さんをお持ちの方であれば、
実感されている方も多いかと思います。
例えば、塾で見ていても、
休み時間なのに気を使ってヒソヒソ声でしゃべる学年と、
お構いなく元気にしゃべる学年とあります。
これは個々の性格ではなく、学年で分かれていますね。
学年によって、乗らせ方というか、接し方も違ってくるので、
なかなか面白いですよ。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月19日
鶏口牛後ってどう思います?
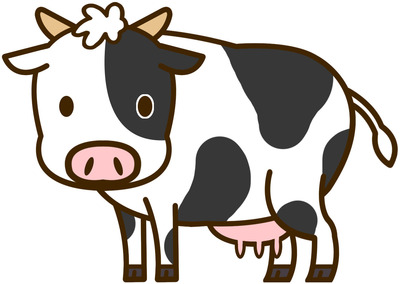
鶏口となるも牛後となるなかれ
大きな集団の下につくより、小さな集団のトップになれ、という意味ですよね。
自分の経験や価値観で言うと、これってどうなのかなって思います。
特に、中学や高校、大学など、若い時は、
大きな集団、自分よりレベルの高い人たちがいる集団の下に
必死で食らいついていく方が、成長できると思うんですよね。
自分の場合はそうで、
いつも自分より出来る人達の集団にいることができたから、
成長できたという自負があります。
ですので自分の子も、そういう環境に放り込んであげたいと思っています。
多感な時期の子どもは、
親や先生が言うことよりも、友達の影響力の方が圧倒的に大きいですからね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月18日
スマホを1回やめてみる

「家で全く勉強しないんです」
というセリフは、保護者面談時によく聞きます。
それで何をしているのですか、聞くと、
最近多い答えは、やはり「スマホ」です。
それはそうでしょうね。
スマホは、持ち主の好きなものしか差し出しませんから、
どっぷりハマっていくのは自明の理です。
賢い人はどんどん賢くなり、
バカはどんどんバカになるでしょう。
後者にならないためには、
スマホを持たせる前から、
入念に準備をしておかなければなりません。
もう既にスマホを手にしているのであれば、
仕方ないですね、
強制的にでもスマホをしない時間を作らせるしかないです。
「別に勉強はしなくていいから、1日○時間だけはスマホやめよう」
というルールを作ってみるのはどうでしょうか。
スマホをしない時間に何をするかまでは強制しません。
でも、そうして切り崩していかないと、
スマホの魔力は絶大だと思いますよ。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただけると幸いです。
2019年01月16日
勉強の報酬はアリか?

ニンジンをぶら下げて勉強させるということは、
本当はしない方がいいと思います。
ただ、報酬が起爆剤になってやる気を出すということも、
事実よくあるケースなんですよね。
ですので、一番いい方法ではないと思いますが、
どうしても勉強しない子には、そんなこと言ってられません。
ニンジンをぶら下げることもアリかな、と思います。
ただし、報酬の中身はしっかり工夫してあげる必要があります。
単純に金銭で解決しようとすると、必ず要求がエスカレートして、
金額を上げないと、効果がなくなってしまうからです。
行きたい場所に連れて行ってあげるとか、
お友達を呼んでバーベキューをしてあげるとか、
品物であげるにしても内容を良く吟味して、
プライスレスなご褒美を考えてあげて下さい。
親としての腕の見せ所ですね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月15日
学習習慣をつけさせるには

どのようにしたら学習習慣をつけさせることが出来るか。
子どもを持つ親なら、誰にでも共通の悩みですよね。
まずやってはいけないのは、
無理やり勉強させることです。
無理やり勉強させると、勉強しない子になる可能性が高いです。
一時的には親の圧力でするかも知れませんが、
学習習慣は将来にわたって大切な習慣ですので、
それでは意味がありません。
では、どのようにしたらいいかですが、
ひとつは、親が勉強をしている姿を見せることです。
学習習慣がしっかりついているな、という子のご家庭は、
話を聞くと、親がよく本を読んだり、何かあるとすぐ調べたり、
勉強をする姿を子どもに見せているご家庭です。
子どもだけに「勉強しなさい」と言ってもダメってことですね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月14日
学習習慣をいつまでにつけるか

学習習慣をいつまでにつけさせるか。
ズバリ言うと、中学生になるまでにつけさせたいですね。
中学校に入ってからでも、ついていなければつけるべきなのですが、
どんどん難しくなります。
というのは、初めに学習習慣をつけさせてあげるのは、
やっぱり親の仕事であると思うからです。
中には、自分から学習意欲を持って取り組む子もいますが、
みなさん(親または本人)の体験談を聞いていると、
最初は親が学習習慣をつけた(親につけてもらった)というケースが
とても多いです。
ですので、親のコントロールが効かなくなる中学校に入る前に、
というのがその理由です。
学習習慣というのは、一生の財産になるものですので、
お子さんへのプレゼントと考えて、贈ってあげて下さい。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月13日
教員の長時間労働

奄美の学校の実態は分かりませんが、
教員の長時間勤務が全国的に問題になっていますね。
2016年度の文科省の調査では、
月80時間以上の時間外労働、いわゆる「過労死ライン」を超える教員が、
小学校で約3割、中学校で約6割もいるそうです。
ほんとにこれ、どうなっているんでしょうね。
こんなことで、生徒の学力を上げる授業なんて出来るわけないですよね。
ある匿名の教員の話では、諸悪の根源は部活動だそうです。
この学校の部活動というシステムも、いいかげん見直す必要があります。
学校の先生が指導するということに、無理がでてきていますからね。
放課後の学校の施設を開放して、
どんどん民間の力を借りればいいのにと思います。
特に都市部なら、いくらでも手が上がるんじゃないでしょうか。
先生方には、まず学力をしっかりつけることに専念してもらいたいです。
でも、学校ってなかなか変わらないですからね、心配です。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2019年01月12日
正負の計算が苦手
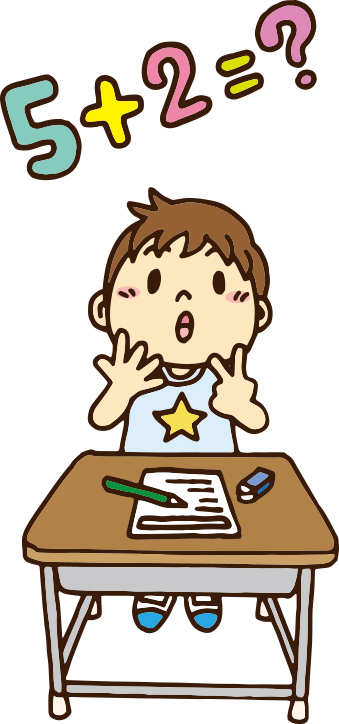
新年はじめの投稿になります。
今年もよろしくお願いいたします!!
さて、今年度も冬期講習が終わりました。
講習会は、基本的にこれまでの復習をするので、
中学生の数学は、どの学年も「正負の計算」から復習する子が多いです。
数学が苦手な子は、軒並みここからつまずいていますね。
特に、足し算・引き算が出来ません。
大きな理由のひとつは教科書だと、私は思っています。
「マイナスにマイナスを加えるとはどういうことか」
のようなことを理解させようと書かれているんですよね。
もちろんそれは大事なことなのですが、
あまり要領の良くない子は、混乱するばかりだと思います。
ですので塾では、もっとシンプルに教えるようにしています。
全ての子に同じように教えねければいけない学校の先生は、
大変だと思いますね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年12月29日
レベルに合った問題を出す大切さ
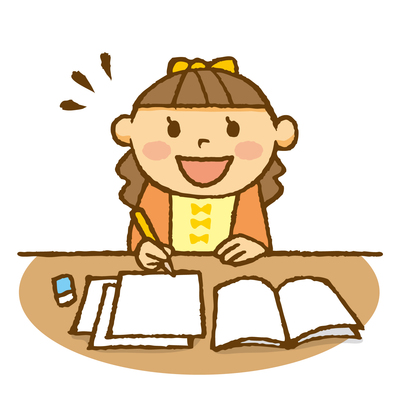
陽平塾は個別指導なので、通常授業時も、
個々のレベルに合った問題は提供できるのですが、
学校の授業が進まない講習会時は、
さらにそれが出来るので、その大切さが実感できます。
なにより、子どもが意欲的に取り組んでくれますよね。
千里の道の一歩目、という生徒も多いので、
成績に跳ね返ってくるまでには時間がかかりそうですが、
こうした小さい成功体験を積み上げることが大切です。
じっくりあせらず、でも結果は出してあげたい、
いつもこのジレンマで葛藤しています。
とにかく昨日より今日、今日より明日という気持ちで、
生徒のモチベーションをあげていきたいと思います。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
【ようへい先生オススメの本】
角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 全15巻+別巻4冊セット
全面新版 学習まんが日本の歴史 2019年版数量限定特典つき全20巻特価セット
学習まんが少年少女 日本の歴史 最新24巻セット
2018年12月28日
歴史は流れをつかむ
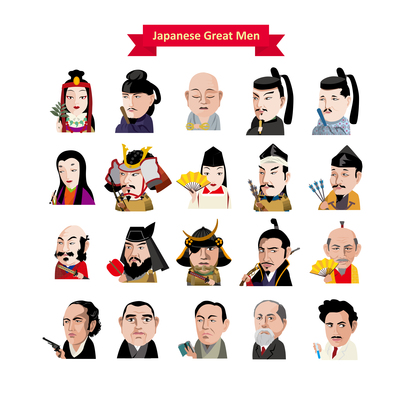
「歴史は流れをつかめ」とは、
使い古された言葉ですが、その通りです。
冬期講習で歴史を教えていても、
大まかな流れすら頭に入っていない子の、なんと多いことか。
江戸時代の次が明治時代だってことくらい常識だぜって感じです。
まず頭にいれるべきは、大まかな流れ。
これをせずにある時代の細部ばかり詳しくなっても、
全体から切り離された断片的な知識は、あまり役立ちません。
全体像がつかめてから、初めて細部が理解できるのです。
スポーツでもなんでもそうです。例えばサッカーでも、
あまり詳しくない人は、ゴールが決まるかどうかとか、
スター選手が活躍したかどうかしか目がいきませんが、
詳しくなると、このチームのフォーメーションはこうで、
こういう戦術で戦っているな、とか分かるようになります。
これと同じように、何事も大から小へと訓練していくものなのです。
そこで、歴史の流れをつかむのにもってこいの教材をオススメします。
『まんが日本の歴史』です。
いくつかの出版社から出ているので、お好みで選ぶのが良いと思います。
価格をはるかに超える価値があると思いますよ。
角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 全15巻+別巻4冊セット
全面新版 学習まんが日本の歴史 2019年版数量限定特典つき全20巻特価セット
学習まんが少年少女 日本の歴史 最新24巻セット
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年12月18日
安定しているから公務員
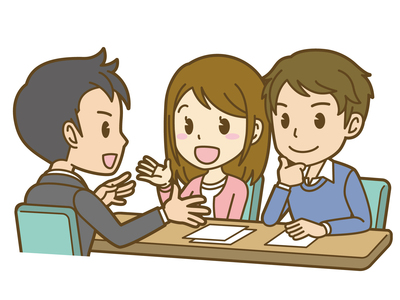
冬期講習受付中!!
電話:090-1882-7129
【陽平塾】冬期講習申込書
【陽平塾】冬期講習申込書(記入例)
いよいよ年の瀬ですね。
中学生にしても高校生にしても、
今まで以上に本気で、具体的に進路を考える時期になりました。
そんな時期によく聞くセリフが、タイトルの、
「安定しているから公務員」
公務員になりたいという夢は、とても良いのです。
ただし、公務員とは、
「国または地方公共団体の職務を担当し、国民全体に奉仕する者」
なのです。
公務員になりたいと言うのであれば、
「みんなに幸せな生活を送ってもらえるように、何かしたいんだ」
という人でなければ困るわけです。
だからこそ住民は、税金で公務員の方にお給料を払っているのです。
自分の生活を安定させたいから、という理由では困るのです。
そこを履き違えている子が、非常に多い。
そこでご提案なのですが、
とりあえずは、大人が、
「公務員は安定しているからいい仕事だよ」
と言うのを止めませんか。
これを言うことは子どもから夢を奪うことになりますし、
第一、いま一生懸命、国民全体に奉仕されている公務員の方に失礼ですよね。
公務員になるという夢を持つのは素晴らしいこと。
でもその理由は、
みんなのために何が出来るのかと考えると、ワクワクする、
でなければいけないはずです。
そう、塾生には伝えています。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年12月17日
日本人はスパルタ教育好き?

冬期講習受付中!!
電話:090-1882-7129
【陽平塾】冬期講習申込書
【陽平塾】冬期講習申込書(記入例)
スパルタ教育、というと随分と使い古された言葉ですが、
この是非については、どのように思われますか。
このテーマは、前提として2つのケースが考えられます。
指導者側の方針に合わせたスパルタか、
指導される側の状況に合わせたスパルタか、
ここで大きく違ってきます。
もう少し分かりやすく言うと、例えば、
生徒の成績や性格がどんなであれ、
とにかくビシビシしごくという方針で先生が進めていく、
という先生主導の問答無用というケース。
それに対して、生徒の成績や性格を見て、
超えさせるハードルの高さを先生がその都度考えながら進め、
その結果がスパルタになるかも知れませんし、
ならないかも知れないというケースもあります。
私は、どちらが良いという問題ではないと思います。
ただ、日本人はけっこう、
問答無用でスパルタ指導する指導者を好む傾向があるような気がしますし、
そういった指導者が結果を出していたりします。
いい例としては、少し前の話になりますが、
先のラグビーワールドカップで快進撃を遂げた
日本代表のヘッドコーチ、エディー・ジョーンズでしょうか。
日本人の我慢強いという性質を見抜いて、
流行語にもなった『ハードワーク』を選手に課し、
見事に結果を出しました。
流行語と言えば、もっと古い例になりますが、
1964年の東京オリンピックで金メダルに輝いた女子バレー、
大松監督のキャッチフレーズは「俺についてこい」でしたね。
では、私(陽平塾)はどうなのかと言いますと、
「生徒の様子を見て対応を変える」です。
相手は未熟な子どもですので、
この子は時間をかけて勉強の楽しさを伝えないとな、
この子はビシビシいってもついて来られるだろう、
などと、生徒によってやり方を変えています。
親御さんのご希望としては、ビシビシやってくれ、が多いので、
もちろんご意向に沿うようにするのですが、
それで勉強嫌いになってしまうと本末転倒なので、
その時はご相談することもあったりします。
脈絡もなくいきなりスパルタにしても、
なかなか思うようにはついて来てくれないもの。
大切なのは生徒、親、塾のコミュニケーションだと思います。
といのが陽平塾の方針です。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。