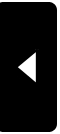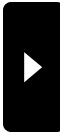2018年12月06日
冬休みにしっかり勉強させるには

冬期講習受付中!!
電話:090-1882-7129
【陽平塾】冬期講習申込書
【陽平塾】冬期講習申込書(記入例)
いよいよ冬休みが近づいて来ましたね。
長いお休みの親の苦悩といえば、
「はやく宿題を終わらせてほしい」
「遊んでばかりではなく勉強もしてね」
ですよね。
いままでも、散々ご苦労されてきたことと思います。
今回は、
冬休みにお子さんに勉強させたい時、
一番大切なことをお伝えします。
それは、
「冬休みは宿題どころではない、ということを理解してあげること」
です。
まずは、私たち大人が、子どもだった頃のことを思い出しましょう。
冬休みは2週間と、夏休みに比べればだいぶ短いですが、
クリスマスに大晦日、お正月と、楽しいことが満載です。
「サンタさんのプレゼントは何かなー」
「大晦日は夜更かししようっと」
「泊まりにくるいとこの◯◯ちゃんと何して遊ぼう」
「お年玉で何買おっかなー」
などなど。
しかも、
お正月は大人たちも正月気分です。
親戚やご近所さんが集まっての宴会もあるでしょう。
まさに正月は、勉強どころではないのです。
まずはこれを理解してあげないと始まりません。
子どもに限らず、大人でも、
「自分のことを分かってくれている」と思う人の意見には耳を傾けますが、
「自分のことを分かってくれていない」と思う人の意見には耳を塞ぐからです。
だからと言って、勉強させなくていい、という訳にはいきません。
じゃ、とうしたらいいんだということは、また機会があればお伝えしますね。
何かヒントになることがあれば嬉しいです。
ま、冬期講習を利用していただければ一番手っ取り早いです。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年11月29日
記憶しておきたいことを記憶するには
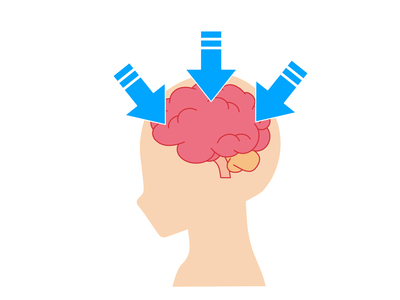
冬期講習受付中!!
電話:090-1882-7129
【陽平塾】冬期講習申込書
【陽平塾】冬期講習申込書(記入例)
各中学、高校の定期テストが終わった、もしくは終盤です。
その是非は別として、定期テストはまだやっぱり、
どれだけたくさんの事を記憶に残せたか、
これが得点を大きく左右しますよね。
そこでひとつ、大切なコツをお伝えします。
数学でも英語でも、どの教科でも同じなのですが、
問題を解いていて分からない、出来ないと思っても、
とりあえず考えて答えを出してみる、コレが大切です。
覚えるのが苦手という子、
とりわけその教科に苦手意識を持っている子は、
問題を解くことを放棄して、
すぐに解説を聞こうとしたり、答えを丸暗記しようとしたりします。
これがダメですね。
人間の脳みそはどんな時に記憶に残してくれるかというと、
自分の予想を裏切られたり、
思い出そうとして思い出せなかったり、
そういう悔しい思いをした時なのです。
数学なら、とにかく今知っている知識で解いてみる、
社会なら、目次を見て内容を想像してから教科書を読んでみる、
そしてそれが間違っていたりする、むしろ間違っていた方がいい。
そんな時に記憶に残っていくのです。
そして、そもそもの大前提として、
自分で出した答えは、自分なりに自信のある答えにする必要があります。
あてずっぽうではダメですが、結果的に正しくなくても全く問題ないので、
自分なりの理屈を考えることが必要です。
根拠なんかなくてもいいのです。
自分は天才だから合っていると思えばいいのです。
とにかく、間違えた時に悔しいと思えるかが大切なのです。
くり返しますが、
出来なくても知らなくてもいいので、とにかくまずは、
自分なりに考えて、予想して、答えを出してみることが大切です。
自信がないからか、面倒だからか、
それをしない子がけっこう目につくんですよね。
それだとなかなか学力は上がっていきません。
ですので塾では、
必ず何らかの答えをひねり出させてから解説するようにしています。
彼らは数年後には、
答えのない人生という問題を解いていかなければいけないので、
こうした習慣を身につけてあげることはとても大事だと思っています。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年11月27日
社会は暗記って本当?
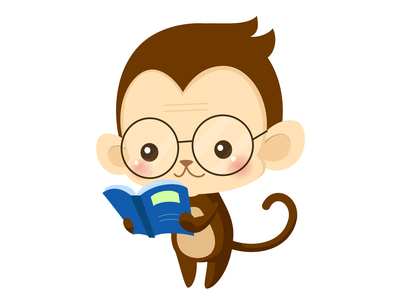
冬期講習受付中!!
電話:090-1882-7129
【陽平塾】冬期講習申込書
【陽平塾】冬期講習申込書(記入例)
社会は暗記科目、だから暗記すればいいだけ、
というセリフをよく聞きます。
でもこれって本当でしょうか。
私の考えでは、2つダウトですね。
まずひとつは、
人間の脳はコンピュータ-ではないので、
意味や脈絡が分からないことを、
そのまま記憶するのは難しいということです。
コンピューターなら、意味不明の文字を羅列しても、
保存ボタンを押せばその通り記憶していてくれますが、
人間には無理ですよね。
ですので、社会は暗記すればいいとは言っても、
その内容が理解できていないと、記憶に残せないのです。
そしてもうひとつ。
こちらの方が重要だと思いますが、
ただ暗記をしたところで、何の意味もないということです。
例えば、
「1192年(イイクニ)作ろう鎌倉幕府」
と覚えたところで、
そんなことは今どきググれば一発で調べられるので、
あまり意味がないのです。
それよりも、
どのようにして鎌倉幕府が誕生したのか、とか、
どのような仕組みで人々を支配したのか、とか、
そのことを理解することが社会を勉強する意味です。
社会は暗記だ、と言ってしまっている人は、
この辺のパラダイム転換が必要だと思います。
どうすればいいかと言うと、
まずは学校の先生の話を良く聞くことですね。
塾の冬期講習でも社会を受講していただければと思います。
そして、それをもとに自分で考えること。
出来るなら、それを先生や友達、家族などにぶつけてみることです。
そこまで出来ればバッチリ、
社会を勉強する本当の意味が分かると思います。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年11月27日
冬期講習のご案内

【陽平塾】では、今年度も冬期講習を行います。
冬期講習も個別指導ですので、
受講科目や回数、カリキュラムは事前にご相談の上、
個別に決定させていただきます。
冬期講習に限りませんが、まずはご連絡をいただき、
面談、カウンセリングをさせていただければと思います。
日程や料金等の詳細につきましては、
下記のリンクから、
『冬期講習申込書』でご確認いただければと思います。
その他ご不明な点は、
いつでもお気軽にお問合せ下さい。
電話:090-1882-7129
【陽平塾】冬期講習申込書
【陽平塾】冬期講習申込書(記入例)
2018年11月22日
奄美っ子のデメリット

どんな場所にでもあることですが、
私たちの住む奄美大島にも、
良いところ、改善したいところがありますよね。
iターンで外から来た私のような人間には、
もしかしたらよりハッキリと見えるのかも知れません。
奄美で子どもを育てるメリットはたくさんあって、
だからこそ私もこの島を選んだのですが、
ここはデメリットだよなー、と思うこともやはりあります。
そのひとつは、奄美の子は、
「どうしたらそうなれるのか、実感できないことが多い」
ということです。
例えば、
「将来Googleで仕事がしたい」
という夢を持ったとしても、
何をどんなふうに頑張ったらそうなれるのか、
見当がつかないのです。
大都市圏、とりわけ首都圏に住んでいると、
Googleでなくても、大企業の管理職だったり、官僚だったり、起業家だったり、
社会の中心でバリバリやっている人がわりと近くにいたり、
知り合いの知り合いくらいにはいたりします。
先ほどの例でいくと、
Googleで働いている知り合いが直接いたり、
そうでなくても、
「GoogleじゃないけどNTTドコモに入った先輩は大学でこんな研究をして、入社面接でこんなプレゼンをして…」
みたいな話がわりと身近にあったりします。
どうしても奄美にいると、そういう機会は少ないですよね。
ここはどうしても、奄美の子にはデメリットだよなー、と思います。
その結果だと思うのですが、奄美の子たちに接していて感じることで、
将来なりたい像のバリエーションがすごく少ないなー、というのがあります。
仕方ないと言えば仕方ないんですよね、
奄美の子たちは、奄美にいる大人たちを見て、将来像を描くわけですから。
じゃあどうしたらいいんだ、ということですが、
この解決はとても難しいです。
が、今はインターネットという素晴らしいものがありますので、
これをフルに活用していくことでしょうね。
まずは親御さんが勉強されることだと思います。
いろいろ調べてみて、
オススメできるサイトをお子さんに紹介するのがいいと思います。
私にもオススメできるサイトはいくつかあるので、
それも参考にしていただけるのなら嬉しいですが、
基本は、親御さんがその価値観で選んでいただくのがいいと思います。
オススメのサイトは、機会があればご紹介しますね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年11月15日
「得するタイプだなー」と思う子

前回の投稿とは反対に、
「この子は得するタイプだなー」という子もいます。
これもズバリ言いますと、『ノリのいい子』です。
ノリの良さって、人生において結構重要なポイントだと思います。
このブログを読んでくださっている大人の方には、
共感していただける方も多いのではないかと思っています。
親の保護下にある小学生~中学生くらいまではあまり感じないかも知れませんが、
自己が確立して、行動範囲も広がる高校生以降の人生になると、
より実感できるようになりますよね。
友だちや先輩、その他、
何かのタイミングで何かのことに誘われたりした時に、
「え、わたしはいいや。」
という反応をする子と、
「とりあえず行ってみよう!」
という反応をする子では、人生がだいぶ変わってくると思うのです。
人生って、結構いろんなところにチャンスが転がっているもので、
とりあえず何でも乗っかってみよう、と思っている方が、
より多くのチャンスに出会えたり、選択肢が増えたりします。
よく、
「将来やりたいことが分かりません」とか、
「好きなことをやれって言われても、それが何なのか」とか、
そんなことを言う子がいますが、
そのタイプはだいたい『ノリの悪い』タイプが多いですね。
その傾向は、小中学生時代にも見えてくるもので、
塾での例で言うと、
「ちょっと手を休めてみんなでゲームをしよう」とか、
「今度こんなイベントがあるみたいだから行ってみれば」とか、
「この本おもしろいから読んでみなよ」とか、
誘われたり勧められた時に、
乗っかってくれる子とくれない子がいて、
こういう時に『ノリのいい子』は将来得するだろうなー、と思う訳です。
何も、みんながみんな、饒舌に社交的に振る舞うべきだ、
というこうではありません。
それに、その子の性格や趣向もあるので、それは尊重するべきなのですが、
経験上、多少無理してでも『ノリ』は大事にしたほうがいいと思った次第です。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年11月13日
「損するタイプだなー」と思う子
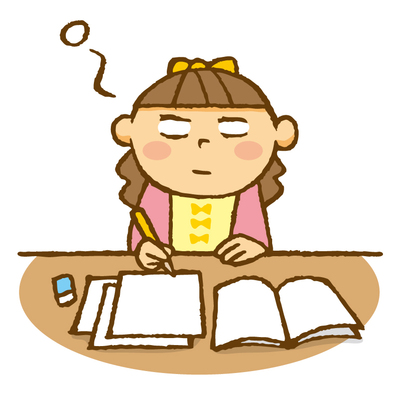
毎日、個別指導塾でお子さんに接していると、
もちろん、いろいろなタイプのお子さんがいます。
そんな中でも今回は、
「この子、絶対損してるよなー」
と思う子の1パターンをご紹介します。
ズバリ、『反応の薄い子』です。
問題の解説をしていても、何も反応してくれないと、
どこまで分かってくれているのか、分かりません。
こちらも一生懸命、顔色を見たり、微妙な反応を見たりしますが、
さすがに判断しきれない場合が多いです。
「分かった?」と質問すると、たいてい「分かった」と言いますので、
この質問にはあまり意味がありません。
こうなると、あとは問題を解かせた結果で判断するしかなくなります。
それはそれでいいのですが、効率が悪いですし、
陽平塾は個別指導だからまだいいでのですが、
普段の集団生活の中では、
じっくり個人と向き合ってもらえるケースのほうが少ないと思うので、
大丈夫かな、と思ってしまう訳です。
それと、教えている側も人間ですので、
こうしたことを心得ていてくれていない人だと、
教えるモチベーションが下がってしまうこともあるでしょう。
以上のような理由で、
反応の薄い子は損をするだろうなー、と思います。
反応と言っても、何も大げさなことではありません。
ただ、『うなづく』だけでいいのです。
でもこの『うなづく』は、とても大事なことです。
大人でもたまに、
うなづきもせず無反応で相手の話を聞く人がいますが、
これってマナー違反ですよね。
そうならないという意味も含めて、
お子さんが「反応が薄い子」の場合には、
早めに改善されることをオススメします。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年08月01日
夕方フレンド聴いてね!!

夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
今回はお知らせを1点。
今日の夕方、あまみFMの『夕方フレンド』というコーナーに出演します。
あまみエフエム ディ!ウェイヴ!
スタッフの方が、このブログを読んで興味を持って下さったようで、
陽平塾のようへい先生、として出演します。
どんな話になるかはノープランなので、
いきあたりばったりで楽しんできたいと思います。
再放送もあるようですので、
お時間があればお聴きいただけると嬉しいです。
放送時間は、午後の6時半頃からということです。
それでは今回はこの辺で。
夕方の6時半に、ラジオでお会い出来たら幸いです。
2018年07月28日
夏バテ予防の栄養素
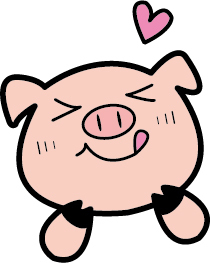
夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
さて、前回の続き、ビタミンB群の中でも、
特に夏バテ予防に効果的な栄養素をお伝えします。
その栄養素は、ビタミンB1です。
ビタミンB1を多く含む食品としては、
豚肉、小麦胚芽や玄米などの精製していない穀類、
落花生や大豆などの豆や種実類などが挙げられます。
また、夏の風物として欠かせない、
うなぎにもビタミンB1はたっぷり含まれています。
この時期、スーパーにはうなぎが並びますが、
これも先人による有効な夏バテ防止の知恵なのです。
そして注目すべきなのは豚肉です。
調理法もいろいろあって使いやすいですし、
ビタミンB1がとても豊富です。
あとは、汗とともに失われがちなビタミンやミネラル補給のために、
野菜や、海藻類などもアレンジできれば最強です。
ちなみに、我が家の豚肉は、
名瀬久里町の国道沿いにある西田商店で買っています。
みなさん、「かごしま子育て支援パスポート」ってご存知ですか。
奄美市に居住し、18歳未満のお子さんがいる家族、
又は妊娠中の方がいる家族の方であれば、
市役所の保健福祉部福祉政策課にいけばすぐに無料でもらえます。
このパスポートがあると西田商店では、
切り落とし肉、通常100g150円(税別)のところ、100g100円(税別)です。
気のいい京都人の大将がいて、しかもお肉めっちゃ美味しいです。
ご存じなかったかたは、下記リンクからどうぞ。
かごしま子育て支援パスポート
西田商店(西田ブタ)
夏バテ予防、ということでいうと、
水分補給についても最後に触れていかなければなりません。
成長期の子供に必要な水分量は、大人の2倍もあって、
体重1Kgあたり100mlになります。
ただし、安易に冷たい清涼飲料水などを与えてしまうのは考えものです。
清涼飲料水の多くは糖分が高いので、炭水化物同じように、
体内に吸収された糖分をエネルギーに変えるために、
ビタミンB1が使われてしまうからです。
夏バテ防止には、栄養素に加えて、水やお茶で適度な水分補給、
清涼飲料水の摂り過ぎに注意するのもポイントです。
豚肉と適度な水分補給で、せっかくの楽しい夏休みを、
元気いっぱいに過ごさせてあげたいですね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年07月27日
食事と夏バテの関係

夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
夏休みが始まって、一週間が過ぎましたね。
部活その他の大会で島外へ出ていた子たちも帰ってきて、
塾としては、ぼちぼち本格的に夏期講習が始まる感じです。
みんなには心機一転、気合を入れて欲しいところですが、
体がバテてしまっていてはどうしようもありません。
そこで今回は、夏バテ予防の方法のひとつをお伝えします。
まずは、「食事」という視点から見た場合、
夏バテはどのようなメカニズムで起こるのかを解説します。
暑いからと言って、冷たいものを飲み過ぎると、
胃腸の動きが鈍ってしまいます。
また、水分を過剰摂取してしまうと、胃液がうすくなり、
消化能力が低下します。
このようになると、本来必要な栄養素が不足してしまい、
夏バテは起こります。
夏バテを予防するためには、
とにかく、しっかり食べることが第一です。
その際、バランスのよい食事を心がけて食べることが大切です。
その上で、特に注目の栄養素をお伝えします。
その栄養素とは、ビタミンB群です。
ビタミンB群は、摂取した糖質をエネルギーに変える働きがあります。
ですので、これが不足すると、
脳へのエネルギー供給が滞りがちになります。
そうなると、眠気を催したり、
脳からの指令で動く末梢神経の働きが悪くなったりしてしまい、
倦怠感を感じるようになります。
だるい・食欲減退・疲れやすいなどの、夏に感じる疲労の主な原因は、
エネルギーや老廃物の代謝不良によるものです。
ビタミンB群をよく摂取して、
体内に疲労物質をためない体質作りをすることが必要です。
ちなみに、そうめんなど炭水化物の多いメニューばかりだと、
取り込んだ炭水化物をエネルギーに変えるために
ビタミンB1がどんどん使われてしまいます。
その結果、だるいなどの夏バテ症状を引き起こすことになりますので、
要注意です。
ビタミンB郡が豊富に含まれる食品は、
うなぎ、豚肉、鯛、ぶり、大豆、モロヘイヤ、玄米、ほうれん草、ごまなどです。
また、ビタミンB群の吸収力を高めるために、
効果的な物質アリシンを含む食品は、
ニンニク、ニラ、ネギ、玉ネギなどです。
これらをバランス良く食べることが大切です。
今回も前回の投稿からの流れに乗って、栄養を話題にしましたが、
また長くなってきたので、
ビタミンB群の中でも特に夏バテ予防に効果的な栄養素については、
また明日お伝えしますね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年07月25日
続・となりの学級崩壊

夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
今回のお話は前回の続編ですので、
前回の投稿をご覧頂いいていない方は、お手数ですが、
まずそちらをお読みいただけると嬉しいです。
では、続きから。
このプロジェクトの中で、
小児科の医師団によって結成されたプロジェクトがありました。
彼らのチームが、
青少年が荒れて散る主因(主な原因)を突き止めたのです。
私のようにアメリカが好きではない方もいらっしゃると思いますが、
アメリカは紛れもなく、世界をリードしている大国です。
その国が、国を挙げて立ち上げたプロジェクトの研究成果なので、
好き嫌い、賛成反対は置いておいて、
この結果を参考にするべきだと思うので、お伝えします。
では、その主因とは、何だと思われますか。
解答の前に、出来れば、予想してみて下さい。
意外な解答であればあるほど、パラダイム転換になって面白いと思います。
私が考える最大の理由は、適切な時期に、
“心のブレーキ”が育まれていないことです。
このことについては、ここではお伝えしきれませんので、またの機会に。
その他、多種多様なご意見があると思います。
そして、かなりの可能性で、それは真実だと思います。
ただ、このプロジェクトチームの解答は、これでした。
シロップ、砂糖、清涼飲料水。
つまり、主因は糖分です。
では、なぜ糖分が主因なのか。その理由は3つです。
1つ目は、糖分を摂取すると、血糖値が上昇するからです。
その結果、脾臓という臓器から、
インスリンというホルモンの一種が分泌されることで、血糖値が低下し、
低血糖症という心身面で不調が出る症状の原因になります。
2つ目は、清涼飲料水には、リンという元素が含まれていることです。
このリンを過剰に摂取すると、カルシウムという、精神を安定させ、
ストレスに対する抵抗力を強めてくれるミネラルの吸収を、
阻害すると言われています。
3つ目は、砂糖が酸性であることです。
この酸性である砂糖を摂取することで、身体は中性を保とうとするため、
アルカリ性への反応が起きます。
この時、あのカルシウムが消費されてしまいます。
その結果、体内に吸収されるはずのカルシウムが消費されてしまい、
カルシウム不足という状態になります。
これらのように、血糖値が下がると、カルシウム不足になってしまうことが、
心のバランスを乱す有力な要因になるのです。
近年、「食育」という言葉も使われています。
私たちは人の親になった以上、子どもを育てていくのに、
こういうところもケアしていく必要が大いにあるのです。
そういった意味で、この間の中戸川先生の講座は本当に良かったですよ。
近いうちにここでも内容を共有しますね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年07月24日
となりの学級崩壊
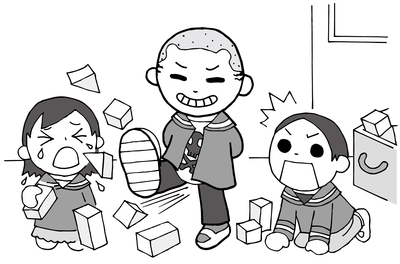
夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
先日、ムラタ薬局さん主催の中戸川貢先生の講演会に行ってきました。
中戸川先生は、食育のプロ中のプロ。
ご存じない方は、とりあえずググッてみて下さい。
メチャメチャ面白かったし勉強になりました。
その内容につきましては、また改めて共有させて下さい。
そこで思い出した話がありまして、今回はその話をさせて下さい。
『学級崩壊』『キレる子ども』というフレーズは、
もう全く衝撃的ではなくなってしまいました。
私は、学習塾の教室長を長く務めてきましたので、
就学前や、小学校低学年向けの指導書も読んできましたが、
現在では、もう普通に、低学年のクラスでも『学級崩壊』が起こっています。
私の経験からすれば、むしろ低学年の方が多いのではないかと思うくらいです。
それ程めずらしい話ではありません。
ですので、お子さんの学校やクラスが既に『学級崩壊』だと聞いても、
私は驚きません。
奄美ではどうなんでしょうね。中学校ではチラホラ聞きますが。
アメリカには、学級崩壊がありません。
なぜかと言うと、アメリカでは、不真面目な生徒や、
人の授業の邪魔をする生徒は、退学処分になるからです。
たとえ公立であっても、クビです。
このやり方には、賛否両論あると思いますが、いかにもアメリカらしい、
合理性を追求したやり方です。
先日、ある本を読んでいたところ、新たな事実を知ることが出来ました。
そんなアメリカも、実は数十年前、
日本と同じように『学級崩壊』が続出するような時期があったそうなのです。
その数、数百万人とも言われるほどの規模で、大問題になりました。
ここで私の趣向をお伝えしても仕方がないのですが、
個人的には、アメリカという国は嫌いです。
ただし、アメリカが優れていると思うことは幾つかあって、
そのひとつに、「自浄作用」があります。
一時、悪いことがあっても、自らの力で修正する能力があります。
その一例にもなりますが、この時のアメリカ政府も、
この青少年が荒れているという異常事態を「国家の一大事」と位置づけ、
その原因を分析するプロジェクトを立ち上げたのです。
またちょっと話が長くなってしまったので、続きは明日といたしましょう。
またお付き合いいただければ幸いです。
2018年07月22日
家庭学習の大切さをどう伝えるか

夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
まず、ひとつお知らせを。
【陽平塾】は個別指導ですので、
夏期講習が開始されてからもお申込は可能です。
お申込時点からスケジュールを作成し、
ひとり一人にとっての夏期講習がスタートします。
部活の大会やその他のことで予定が立たなかった方、
いつでもご相談下さいね。
さて、昨日は結局、台風で休講としたので、
今日から夏期講習がスタートしました。
長い夏休み、基本的には毎日、
机に向かえるようにしたいですね。
そのための夏期講習と無料自習室のなのですが、
塾に来られない場合も、家庭学習はしっかりさせたいですよね。
そのためには、学校や塾、習い事などの宿題、課題を、
子どもがどのように捉えているかが大変重要なことになります。
そして、その重要さを、子どもは分かっていません。
まずは、親が重要だと捉えていることを伝える必要があります。
では、どうすれば伝わるというと、
子どもが勉強をしている時はテレビを消すとか、
宿題をやる時間に買い物に連れ出さないとか、
大人ではなく、
子どもの都合に合わせて環境を整えてあげることが必要です。
口だけでは伝わりません。
ご家庭で一緒に過ごす時間が長くなる夏休み、
いろいろ目につくところも多くなって大変ですが、
ぜひ、上手に伴走してあげて下さい。
新学期、子どもがスムーズに走りだせるようにしてあげたいですね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年07月15日
記憶力の旬って何歳くらい?

夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
ズバリ答えから言ってしまうと、記憶力の旬は7~12歳くらいです。
もちろん個人差はありますが、
このくらいの年齢の子が、同じ文章を1カ月音読を続けると、
すっかり覚えてしまい、本を見ずに暗唱出来るようになります。
記憶力は、7~12歳頃に著しく発達すると言われていて、
この時期の子どもの記憶力には、目を見張るものがあります。
私の教え子に、こんな子がいました。
その子は、とてものんびり屋で、国語が苦手な男の子でした。
『ひとつの花』という、戦争をテーマにしたお話があるのですが、
これを、毎日音読するという課題を出し続けました。
なぜ、『ひとつの花』なのかというと、本人が選んだからです。
題材は何でも良かったのですが、
読みたいものを読ませた方がいいだろうと、
単純にそういうことです。
ただ、『ひとつの花』は、
教科書で14~15ページにもわたる長文です。
学校の授業であれば、1カ月くらいかけて、扱っていく題材です。
暗唱するには高めのハードルと言えます。
ある日、お母さんから、嬉しい報告がありました。
学校の先生と、何かの話の流れから、
彼が『一つの花』を毎日音読して暗唱していることが話題になったそうです。
とても信じられなかった先生が、
休み時間に暗唱してもらうことにすると、彼の口から、
すらすらと物語が出てきます。
後半、少しつまったりすると、
周りの友達から声援が飛びました。
結局、彼は全文を暗唱し、
クラス中から拍手喝采を浴びたのだそうです。
学校の先生が、「驚きを通り越して、感動しました」と、
報告してくれたのだと、お母さんは嬉しそうに話してくれました。
この経験が、彼にとって大きな意味を持ったことは、
言うまでもありません。
鍛えれば、子どもの記憶力は、ここまで発揮されるのです。
このように、音読は全ての学習の基礎であり、
子どもの記憶力を高める効用があります。
ぜひ、ご家庭でも、音読を実践してみて下さい。
最後に、親子で音読できる本をご紹介しておきます。
⇒ 『親子音読ペア絵本 いっしょによもうよ』
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年07月14日
7月13日の記事
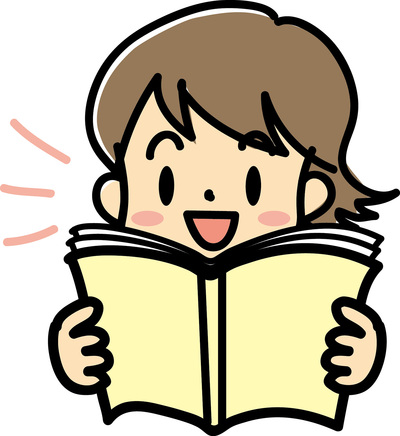
夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
前回(昨日)の話の続きです。
今回からご覧になった方は、お手数なのですが、
ひとつ前に投稿した記事をお読みいただけると嬉しいです。
学校の勉強においても、国語に限らず、
あらゆる教科書を音読することには効果があります。
黙読だけでは、何を問われているのか分からなかった算数の文章問題も、
何度か声に出して読ませているうちに、
だんだん意味が分かるようになってきたりします。
逆に、勉強で遅れを取ってしまっている子は、
例外なく、きちんと教科書を読むことが出来ません。
ボソボソ、ポツリポツリと、雨だれ式に読むことしか出来ないので、
何が書いてあるのかが理解できません。
当然、授業にはついていけなくなります。
こういう子どもにこそ、しっかりと音読をさせてあげたいです。
最初は、親がお手本を示してあげるというのも良いと思います。
途中でつっかえなくなるまで、何回でも何十回でも音読させます。
何日かかっても良いのですが、
延べ30回を1つの目安にすると良いと思います。
ある程度しっかり読めるようになったら、
まずはそれを認めて、褒めてあげましょう。
そして、「どこが分かりにくかった?」と、質問して見て下さい。
自信を持って読めるようになると、
理解出来ていないところが、だんだん整理されてきます。
音読をする時につっかえやすいところが、
つまずきのポイントでもあります。
そこが絞れてくると、
適切な対策を立てることが出来るようになるのです。
学習のつまずきのポイントを、子どもから聞き出そうとしても、
無理な話です。
つまずいている子どもに対して、最も重要なのは、
「自分はどこが分かっていないのか」
「分かるために何をすれば良いのか」を、
はっきり示してあげることです。
‘何をどれだけ頑張るか’が明確にすることが、
やる気を起こさせる一つの方法です。
この中身が適切で、良い結果を手に入れた時に、
子どもは自信をつけます。
そのためにも、テキストや教科書を、しっかりと音読させて、
聞いてあげて欲しいのです。
実は、記憶力には“旬”というものがあって、
その時期に鍛えてあげるのが一番いいのですが、
その時期を外していても、もちろん鍛えたほうがいいし、
能力を伸ばすことは出来ます。
かくいう私も43歳になりましたが、まだまだ鍛えていますよ!
またまた話が長くなってきたので“旬”の話は次回(明日)に。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年07月13日
子どもに音読させよう

夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
学校や塾などの宿題で、
音読が出題されることがあるかと思います。
多くの場合、おうちの人に聞いてもらって、
サインか何かをもらってくるというチェック方法なので、
手を抜こうと思えば、手を抜き放題だと思います。
もちろん、手を抜けるなら抜きたいのが子どもなので、
そのクオリティーは親にかかっています。
今回は、音読の重要性を再度認識して、
ぜひ子どもに音読をさせ、聞いてあげて欲しいというお話です。
東北大学で脳科学を専門にしている川島隆太教授。
脳科学ブームの立役者で、メディアへの露出も多いので、
ご存知の方も多いと思います。
DSの脳トレゲームも話題になりました。
川島先生によると、人間の活動の中で、
最も脳を活性化させているのが音読だそうです。
音読は、口や腹筋を使って発声し、
その声を耳で聞くことになるので、
目で文字だけを追う黙読に比べ、
身体の多くの部分を使っていることになります。
つまり、それだけ脳をたくさん使っている、ということです。
川島理論への批判も、存在しているのは確かですが、
少なくとも、音読が脳をたくさん使うことは間違いありません。
私は、勉強を教えるという仕事をしてきたので、
どうやったら脳ミソを鍛えられるかということについては、
平均値以上は学習してきたつもりですが、
子を育てる親としても、そのことはとても有意義だったと思います。
このブログをお読みいただいている皆さんにも、
お子さんのために、ぜひ学んでおかれることをオススメします。
手始めに、一冊の本をご紹介します。
私のような素人でも、十分に楽しんで理解できる内容でしたので、
気軽にに読めると思います。
川島教授と、文学者の安達忠夫教授の共著です。
⇒ 『脳と音読』
勉強につまずきやすい子ほど音読をして欲しいです。
ただ、ちょっと話が長くなってきたので、続きは明日にしますね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年07月12日
親子の会話をはずませるコツ

夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
これから夏休みに入ると、
子どもと過ごす時間が普段より長くなりますよね。
せっかくですから、会話をはずませて、
コミュニケーションをたくさん取りたいところです。
ともすると、悪いところばかり目について、
ガミガミ・タイムになってしまいがちですが、
そうならないように心がけたいものです。
そこで今回は、
会話を引き出すというか、はずませるコツをお伝えします。
まずは前提として、
親が会話の主役にならないように注意することです。
会話は子どもの発言を促すためにする、
という意識を持つことが大切です。
「今日は学校で何があったの?」
というような、ふわっとした質問は、
「別に普通だけど」
のような答えを引き出してしまいがちなので、
もう少し工夫が必要です。
そこでオススメなのは、
逆説的に聞こえるかも知れませんが、
まず親が自分の話をする、ということです。
「今日、お母さんはこんなことがあってね・・・」
というように、
日常の些細なことを子どもにまず伝えてあげて、
会話のハードルというか、
こんな感じのことでいいから今日あったことを教えて、
という見本を示してあげるのです。
あくまでも、子どもの発言を促すことが前提ですので、
親が主役にならないように注意しながら、です。
心理学的には、返報性の法則というもので、
コツをつかめば効果的に使えると思いますよ。
ぜひ実践してみて下さい。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年07月11日
モンテッソーリって何?

夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
中学生にして、前人未到の最多連勝記録を達成して大注目を浴びた、
プロ棋士の藤井聡太さん。
強さの秘訣は、他のプロ棋士をも唸らせる、ずば抜けた集中力です。
その原点にあると言われているのが、
彼が3歳で入園した地元の幼稚園が取り入れていた
「モンテッソーリ教育」です。
かのマイクロソフト創業者、ビル・ゲイツも学んだというこの教育法、
最近ふとしたきっかけで、「モンテッソーリ教育」について学び直す機会があったので、
今回はモンテッソーリ教育について、簡単にご説明したいと思います。
そもそも、モンテッソーリというのは人の名前です。
イタリアのローマで医師として働いていたマリア・モンテッソーリが、
20世紀の初頭に考案した教育法をモンテッソーリ教育と呼んでいます。
モンテッソーリ教育の特徴は、とにかく常に子どもを観察し、
そこから学んでいこうという姿勢が貫かれていることです。
子どもがダダをこねている時、
子どもが一心不乱に何かに集中している時、
子どもが何度も何度も同じことを繰り返している時、
その時その時の子どもの心の中にある思いや願いを、
的確に読み取ることを基本としています。
そのため、子供たちが安心して自由に遊び、
作業のできる環境整備が重視されています。
教室の状態や教具、もちろん教師の存在も、
大切な環境の一つとして考えられています。
整った環境のなかで自主的に遊ぶ子どもたちを、
とにかく注意深く観察することが、
この教育法の重要な要素なのです。
モンテッソーリ教育を受けた有名人は数えきれませんが、
特に著名な方々だけ挙げても、
アンネ・フランク(「アンネの日記」著者)、
ジェフ・ベゾス(Amazon.com創立者)、
サーゲイ・ブリン(Google創立者)、ラリー・ペイジ(Google創立者)、
ジミー・ウェールズ(ウィキペディア創設者)、
ウィル・ライト(シムシティ開発者)、
ピーター・ドラッカー(社会学者)、
ジョージ・クルーニー(映画俳優、監督)、
ウィリアム王子(イギリス王室成員)、ヘンリー王子(イギリス王室成員)、
そして藤井聡太(将棋棋士)と、そうそうたる顔ぶれですね。
モンテッソーリ教育法は主に乳児、幼児、園児あるいは児童を対象にしていますが、
欧米では、小学校や中学校、高等学校でも行われているようです。
日本では、主にカトリック系の保育園や幼稚園で多く行われています。
小学校のお受験対策、英才教育や早期教育という幼児教育と誤解されているケースが多いのですが、
そもそものモンテッソーリ教育は、知的発達障害の治療教育や、
貧困家庭の子どもたちへの教育を目的に発展させてきた教育法なのです。
モンテッソーリ教育について、さらに詳しく知りたい方は、
下記のリンクから日本モンテッソーリ教育綜合研究所のページをご参考になって下さい。
日本モンテッソーリ教育綜合研究所
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年07月10日
決意は右足に乗せて

夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
もうすぐ夏休みですね。
「この夏休みは、しっかりと復習をしよう」
とか、
「最初の1週間で、宿題は全部やっちゃおう」
とか、
休みに入る前は、いろいろ計画を立てることと思います。
そう決めて、頑張るぞって考えている時は、
自分で自分に期待して、とても楽しい気分になるものです。
ただし、人間の意志というのはめちゃくちゃ弱いものなので、
いざ始めてみると、辛くつまらない作業が続いて、
いつの間にか最初の計画が有耶無耶になってしまうことって、
よくありますよね。
そうならないためには、どうしたらいいか。
それは、具体的な行動に移すことです。
例えば、
ついつい勉強時間にマンガを読んでしまうのであれば、
マンガを物置にしまうとか、思い切って捨ててしまうとか、
そういうことです。
つまり、
「勉強をしよう」と決めたのであれば、
勉強をせざるを得ない環境を作ってしまうことです。
塾に通ってきてくれるのであれば、
夏期講習の授業を入れてくれてもいいですし、
毎日必ず自習室に来ると決めてくれてもいいです。
塾こそ「勉強せざるを得ない環境」ですからね。
ただ決めるだけか、具体的な行動に移すことが出来るか、
これで、夏休みの成果は大きく変わります。
決意は右足に乗せて、具体的な1歩を踏み出して下さい。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年07月09日
まるごと復習法
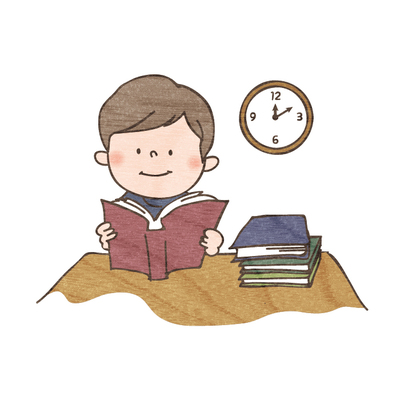
夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
前回の投稿でお伝えした通り、勉強するなら復習が一番大切です。
予習、復習といいますが、時間でいうと、
例えば学校や塾で新しいことろを1時間で習ったとすると、
予習に必要なのは多くても30分くいらい、
復習には4時間くらいはかけたいよね、という感じです。
では、どのように復習すれば良いのでしょうか。
ひとことに復習、と言われても、
実際にどのような方法で勉強すればいいのって、
悩んでいる方も多いと思います。
その答えはズバリ
「授業をまるごとそのまま繰り返す」ことです。
これが理想です。
まずは授業に集中して取り組んで、さらに、
その授業を動画や音声で記録しておいて、
それを繰り返し見たり聴いたりして復習できれば一番いいです。
私自身も、例えば大学受験勉強の時は、
予備校の授業をまるごとカセットテープ(当時)に録音して、
その日帰ってから、その次の日、翌週の授業に行く前の3回、
繰り返し聴きながらテキストやノートを見なおして復習していました。
とは言え、学校の授業を録画して復習することは難しいでしょう。
ですのでそこまではしなくて良いのですが、
まずは集中して授業を聴くこと、
そして、
その時のことを思い出しながら教科書やノートを見直すこと、
「あの時、先生はあんなこと言っていたな」とか、
「この後、この問題を解いて答え合わせをしたっけ」とか、
授業の流れを反芻して、同じように勉強できたらベストです。
同じ問題を同じように解くだけで十分です。
人間の記憶はそんなに長く持ちませんから、
基本的にはその日のうちに行うのがいいと思います。
今回、細かい話は抜きにしますが、
この方法は脳科学的にも実証されていることなので、
安心して実行してみて下さい。
復習の方法は簡単なのです。
まるごとそのまま、同じように同じことを繰り返す、
これが基本です。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。