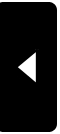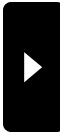2018年07月05日
忘れるのが早まっちゃう勉強法

夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
中学生・高校生は定期テストが終わりましたね。
各テストは、子ども達にとっても私にとっても、勝負の場です。
ですので、私は戦略を立てて、
その子が今いちばん結果を出せそうな授業をしたり、
勉強法をアドバイスしたりします。
それでも結果の出ない生徒は、残念ながら、どうしてもいるのです。
中でもいちばん残念なケースのひとつは、
「ここまでは完璧だったのに、そこも間違えちゃったんだー」
です。
ただ、そのメカニズムは、脳科学的には明快です。
脳に覚えたことを忘れさせようとするならば、
一番効果的なのは、新しい記憶を追加することです。
キャパ(容量)を超えて、無理に詰め込もうとすればいいのです。
先ほど例に挙げたケースは、
「今まで完璧だったところ」までがその子のキャパだったのに、
「テスト範囲はここまでだからやらなきゃー」と、
直前に詰めこんだ結果である可能性が高いです。
もちろん私は、
「今回は、ここまでを完璧にしておくだけでいいからね!」
などと伝えているのですが、
それはまあ、
直前にアセってその先まで手を付けてしまう気持ちは分かります。
でも、それは逆効果である場合があります。
新しい記憶と古い記憶は、必ずお互いに影響を与え合います。
いい具合にいけば、相乗効果を発揮しますが、
悪い具合にいけば、お互いを相殺してしまいます。
だからこそ、
「今日の授業で進めるのは、この辺までにしようかな」
とか、
「この子は今回のテストでは、ここまでを頑張らせよう」
とか考えて授業をしているのですが、
どうしても伝わりきらない場合もあるのが正直なところです。
残念がっていても仕方がないので、
結論というか、解決策をお伝えします。
テスト前はもちろん、ふだんの勉強でも、
一番大切なのは復習です。
学校なり塾なりで学んだこと、それを1とするならば、
4以上は復習にあてて下さい。
復習の大切さについては、また改めてお話しますね。
せっかく勉強するなら、出来るだけ効果的な方法でやりましょう。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年07月04日
先生に家庭学習の様子を伝えよう

夏期講習受付中!!
※日程は下記リンクの申込用紙でご確認いただけます。
※詳細は 090-1882-7129 までお問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
あるお母さんの話です。
「どうも繰り下がりの引き算が苦手みたいです。」
「8の段の九九を覚え切れていません。」
「学校の漢字テストで半分しか出来ませんでした。」
お子さんが、勉強が理解できていないようだと分かると、すぐ事細かに教えてくれました。
ぶっちゃけ、こういうお母さんは、
塾にとっては気を使う存在ではあるのですが、
おかげで、その子のつまずきを見逃すことなく、
順調に成績を伸ばすことが出来るのも事実です。
ですので、お子さんのため思うなら、学校や塾などに対して、
出来るだけウルサイ保護者になる事をオススメします。
遠慮はいりません。
また、家庭学習をどのようにやっているかは、
先生にとっては大変重要な情報です。
家庭での勉強の様子と、
授業中の勉強の様子が違うというケースは、多々多々あります。
先生との面談時には、授業の様子を聞くだけではなく、
家庭での様子もしっかり伝えた方が、子どもにとってプラスになります。
家庭での学習を通じて、親と先生がうまく連携することで、
子どもの学習を支えていくことができます。
逆に言えば、それが出来る先生を、
しっかり選ぶのが親の大事な仕事です。
学校の場合は選ばせてもらえるなら、ですが。
少なくとも塾は選べますね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年06月18日
夏期講習のご案内

今年度も夏期講習のご案内です。
陽平塾は、すべてのお子さんに対して、
「旧知親しいの友人のお子さん」
として接することをモットーとしています。
ですので、塾に来ていただいた場合は、
勝手に親しい友人と思っています(もちろん節度はわきまえますが)ので、
悪しからずご了承下さい。
“夏を制する者は受験を制す”とは、
ずいぶん昔から言われてきたフレーズですが、
その本質は、
“いかに自分をコントロールできるか”
ということだと思っています。
長い夏休み、24時間まるごと自由に使える日が、
ほぼ40日間。
どのように使うかで、その後の人生が大きく変わりますよ。
ぜひ、そのお手伝いをさせて下さい。
【陽平塾夏期講習2018】
期間:7/21(土)~8/28(火) ※8/29は統一模試
時間帯:9:00~17:10までの90分5コマのうちご都合のよい時間帯
形式:個別指導・スケジュールはオーダーメイドで作成
料金:1コマ2,160円、教材費は実費分のみ
申込:下記のリンクから申込用紙をご確認の上、お問合せ下さい。
【陽平塾】夏期講習2018
【陽平塾】夏期講習2018(記入例)
詳細は、お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせ下さい。
電話:090-1882-7129
メール:yohei.amami@gmail.com
この夏こそは「やり切った!」と言える夏にしたいですね。
それでは今回はこの辺で。お問い合わせ、お待ちしております。
2018年06月17日
夏期講習のご案内(予告)

陽平塾では、今年度も夏期講習を行います。
形式は例年通り、オーダーメイドの個別指導です。
詳しい日程と時間割は、明日10時に、このブログでご案内します。
詳細は、お電話またはメールにてお問合せ下さい。
電話:090-1882-7129
メール:yohei.amami@gmail.com
受講するかどうか決めるのに事前に体験授業を受けたい、
講習会前に入塾して授業を始めたい、
まずは無料学習カウンセリングで話を聞きたい、
どのようなご希望でも結構ですので、
お気軽にお問合せいただければと思います。
多くの奄美っ子に会えることを楽しみに待っています!!
よろしくお願いします。
2018年06月17日
エアコンとの付き合い方

そもそも私は、エアコンは使わない方が良い派です。
なぜなら、子供を第一に考えた時、
体の健全な成長のために、デメリットが多いからです。
人間の体には、体温調節機能があります。
暑い時に汗をかいて熱を放出したり、
寒い時に鳥肌を立てて熱の放出を抑えたりすることで、
この機能は発達していきます。
しかし、一日中エアコンで調節された室温で過ごしていると、
この機能が健全に発達しません。
適応力や抵抗力が弱くなってしまい、
すぐに風邪をひいたり、熱中症になったりと、
体調を崩しやすい体になってしまします。
発達段階にある子供たちの体にとって、
これはデメリットですよね。
ですので、そもそも使わないのが一番、と思っています。
子どもには、
「あれは他人を暑くして、自分が涼しくなる機械なんだよ」
と、教えています。
ただし、そこは南国奄美大島。
奄美でなくても暑い夏は、それでもやはりエアコンを使った方がいい、
というケースもたくさんありますよね。
(もちろん塾では使っています。)
だったらこうやって使いませんか、というご提案です。
エアコンのある子ども部屋は涼しくて快適。
子どもにとってはまさに天国です。
でも、ずっと閉じこもったり、冷やし過ぎたりしてしまいがちなので、
子どもに任せきりにしない方がいいと思うのです。
それに、子ども部屋のエアコンを上手に使えば、
いろいろなことを教えるチャンスにすることが出来ます。
たとえば、
子ども部屋のエアコンと、リビングのエアコンを
時間差で動かすようにします。
あるいは、寝苦しい就寝前のみ動かすなど、
子ども部屋では、あまり使わないようにします。
そうすれば、子ども部屋でエアコンが動いていない時間は、
涼しいリビングに子どもは集まってきます。
リビングで宿題をやらせましょう。
私は、思春期前の子どもは宿題もリビングで、と思っています。
彼らにとっては、すぐ近くに話せる相手がいる、頼れる人がいる、
これが必要なんですよね。
親が視界に入ることで、安心して勉強に取り組むことができ、
疑問にぶつかったときも、親と一緒に取り組める、
部屋でひとり集中させるより、こっちのほうが良いと思います。
エアコンを使う時間帯についてはあらかじめ話し合い、
それを親子の約束としてしっかり守らせることで躾にもつながります。
近年の社会情勢に合わせると、
「電気の大切さ、電気を使うことの意味」を教える
絶好のチャンスと考えることも出来ます。
むやみに冷やさないよう温度調節をする、衣服も合わせて調節するなど、
うまく工夫することが節電につながり、
環境のためになることも教えられます。
小さな頃から、折にふれて話し実行させることで、
地球環境を意識できる大きな人に育ててあげたいですよね。
ご提案、いかがでしたでしょうか。
「宿題はリビングで」というトピックについては、
また改めてお話させて下さい。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年06月15日
まず身に付けさせてあげたいもの

塾でいろんな生徒を見ていると、
あー、この子はこのままじゃ成績上がんないな、
と思う子がいます。
どんな子かというと、とにかく自信がない子です。
逆に言うと、何かに自信を持っている子は、
何かのきっかけや、何かのタイミングで、
時間がかかる場合もありますが、必ず成績は上がってきます。
その自信は、勉強ではなくても全然構わないのです。
縄跳びが上手いでも、絵が上手でも、カルタ取りが上手でも、
友だちがたくさんいるってことだって良いのです。
自信があるってことは、そのことについて、
過去に成功体験を積んできたということです。
「やれば出来る」という体験をしたということです。
勉強であれ何であれ、これがまず最初に大事なんですね。
塾に来てくれている子に私がするべきことは、
勉強を通してそれを体験させることですから、
いつもそれを考えて授業をします。
基本的には、スモールステップで、
小さな成功をたくさん積み重ねてあげることを考えます。
そのためには子どもをよく見て、タイムリーに、
「あ、この前できなかったこの問題、今日はできたね!」
と、一緒に喜ぶことが重要です。
これが出来るので、陽平塾は個別指導にしているのですね。
それと最初、教科は1教科に絞ることが多いです。
まずは1教科に絞って、成功体験をつませることが先決だからです。
それに、何か一芸に秀でるということは、
他の全てを一変させるほどの自信につながるケースが多いです。
とにかく勉強でも何でもいいから、
「やれば出来る」という自信を身に付けさせてあげること、
これがないと始まりません。何も始まりません。
年齢、学年問わず、勉強であるかないかを問わず、
お子さんが何かひとつ「これ、自信ある」
と言えるものを持てるようにしてあげたいですね。
結局はそれが、学力アップの土台にもなります。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年06月14日
お手伝いで学力アップ

ある女の子の話です。
私の教え子である、その女の子は、
当初は、あまり理解が早い方ではありませんでした。
しかし、授業を重ねていくうちに、見る見る理解力が高くなり、
はっきりと学力が上がっていきました。
テストも満点を取ることが普通になり、
本人も、以前より明らかに自信に満ちた雰囲気に変わっていきました。
保護者面談時、お母さんは、しきりに「塾のおかげです」と、
感謝の気持ちを伝えてくれました。
しかし、それだけではないことは、私にはよく分かっていましたので、
謙遜するお母さんから、何とかその秘訣を教わろうと思いました。
よくよく聞いてみると、以前に私が、
「お手伝いさせることの大切さ」をお伝えしたことを覚えていてくださり、
それを素直に実行してくれていたようなのです。
責任感を持たせる、自信を付けさせる、生活にメリハリをつけるなど、
お手伝いのメリットは多くあります。
ただ、このお母さんが素晴らしかったのは、そのお手伝いの合間に、
「今日、学校で何があったの?」と、
お母さんから語りかけることを意識していたことです。
決して尋問のような雰囲気ではなく、
子どもが話しやすい雰囲気作りも意識したそうです。
すると、子どもからも、学校であったこと、友達のこと、先生のこと、
色々な話を以前に増してしてくれるようになったそうです。
学校の授業内容についても、「今日習った○○が分からない」といように、
教えてくれるようになったそうです。
このタイムリーさは、とても大きなポイントです。
ゆっくりタイプの娘の性格を知り尽くしているお母さんですので、
娘のリズムに合わせてじっくりと話を聞き、分からないところを教え、
教えきれないところを「塾で先生に聞いてごらん」と言って、
塾に送り出してくれていたのです。
絶対に、「どうして分からないの!」と、責めたりはしなかったそうです。
これ、言葉で言うほど簡単ではないですよね。
こうして、話を聞き、お手伝いをさせながら、
子どもと上手にコミュニケーションを取っていたことが、
急成長の最大のポイントであることが分かったのです。
いつもブログで偉そうな話を書いている私ですが、
我が子にどれでけしてやれているか、というと反省ばかりですので、
耳が痛いというか、大変参考になるお話でした。
みなさんはいかがでしたか。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年06月13日
アウトプットが大切

今回は、けっこう多くの子がやってしまっている、
効率の悪い勉強法のひとつをご紹介します。
ズバリ結論から言いますと、
“アウトプットの少ない勉強法”です。
どういうことか説明します。
人間の脳というのは、
インプットよりもアウトプットした時のほうが、
内容が定着するようにできています。
例えば、特に社会はそうなりがちですが、
一生懸命に教科書やノートを見て覚えたのに、
それで終わりにしてしまったり、
ちょこっとしか問題を解かないで終わりにしてしまったりすると、
内容が定着しないのです。
大切なのは、何度も何度もアウトプットすること、
つまり、問題を繰り返し解くことで、
そうすると効率よく内容が定着するのです。
ですので、頑張って読み込んで覚えることは大事なのですが、
それより大事なのは、たくさん問題を解くことです。
問題は、同じ問題の繰り返しでも大丈夫です。
もちろん、より多くの問題を繰り返し解いたほうがいいです。
それと、例えば、
10問の問題を満点取れるまでやろう、
と決めて3問間違えたとします。
たぶん一番多くの子がしている勉強法は、
その間違えた3問を覚えなおして、
その3問だけをもう一度テストし直します。
それでも悪くはないですが、
合っていた問題も含めて全問テストし直したほうが、
より効果的です。
ポイントは、
とにかくアウトプットの量を増やすことなんですね。
ぜひ参考にしてみて下さい。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年06月05日
サッカー日本代表の若手育成

今回はちょっと、私の趣味にまつわる話を。
今年開催されるサッカーのロシアW杯日本代表が発表されましたね。
私は少年時代からずっとサッカーをしてきた人間ですので、
もちろんこの話題には、かなり注目しています。
日本代表のサッカーの中身とか、監督選びのやり方云々についても、
言いたいことはガッツリあるのですが、
ここでは、「若手育成」というキーワードで考えてみたいと思います。
今回の日本代表選手の平均年齢は28.3歳。
前回のブラジルW杯に照らして考えると、2番目の高齢チームです。
1番目は28.5歳のアルゼンチン。
前回は準優勝という成績を残しましたが、今回の予選は大苦戦しています。
サッカー界はもとより、どの世界においても、
若手育成というのは、最重要課題なのです。
しかし日本のサッカー界では、若手が育っていない。
ハリルホジッチ前監督も積極的に登用して来なかったし、
西野現監督を含む協会がそれを要望しても来なかった。
若手が育たないは、大人の責任なのです。
若手は若手なのですから。
経験のある大人が、手を引いてあげてこそ才能が花開くのです。
育成システムなど関係なく、突然ブワッと現れる天才もいるかも知れませんが、
少なくともサッカー界では、
メッシにしてもクリロナにしても、しっかりとた育成システムで磨かれた選手たちなのです。
みなさん、今度のW杯の日本代表の戦いぶりももちろんですが、
今回の反省点を活かし、その後の日本サッカー界(特に協会)が、
どのように若手を育てていくのか、目を光らして下さいね。
そうしないと、日本のサッカーは強くなりませんから。
ということで、
私の趣味にまつわる話にお付き合いいただき、恐縮です。
大切なお子さんの将来を預かる仕事をしている身として、
改めて考えるきっかけになった、という次第です。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年06月04日
なぜ忘れてしまうのか

6月に入りました。
今月は、中学校も高校も、定期テストがありますね。
テストに向けた勉強では、
たくさんのことを記憶していく作業が欠かせません。
そして、記憶したことをできるだけ忘れたくない。
でも、せっかく覚えたのに、何で忘れちゃうんだろう、
自分って頭悪いのかな、とか思ったことはないでしょうか。
そこで今回は、記憶のメカニズムを簡単に解説します。
ます記憶には、「短期記憶」と「長期記憶」があります。
パソコンに例えて説明すると、
私は今、パソコンでこの文章を打っているのですが、
電源を落とせば消えてしまいます。
これは「短期記憶」です。
そこで、消えてしまっては困る文章は、
保存ボタンを押して、ハードディスクというところに保存します。
これが「長期記憶」です。
こうして「長期記憶」に保存された内容は、
いつでも取り出してくることが出来るようになります。
ですから、いかにして短期記憶を長期記憶にするかがポイントなのですが、
人間の脳で保存ボタンの役割をしているのが、「海馬」という場所です。
この「海馬」が、必要だと判断した情報だけが、
長期記憶として脳に保存されていくのです。
この判断、自分の意志で下せるのならいいのですが、
残念ながらそうはいきません。
では、どういった情報が必要と判断されるかというと、
「生きていくために絶対必要なもの」です。
命に関わることでないと、脳は長期記憶に保存してくれないのです。
ということで、
人間の脳というのは、そもそも忘れるようにできているのです。
覚えるよりも、忘れる方が得意なのですね。
ですから、覚えられないといって落ち込む必要は全くありません。
むしろ脳科学的に、とても優秀な脳ミソといえます。
そしてこれは、誰の脳でも同じことなのです。
とは言え、
だからといって何も覚えないという訳にはいかないので、
じゃあどうするんだって話なのですが、
要は、脳をだますんですね。
ちょっと長くなりましたので、その話はまた別の機会に。
またお付き合いいただければ幸いです。
2018年06月03日
子どもの睡眠を大切に(その2)

前回に引き続き、子どもの睡眠時間の話です。
今回は小学生からお話しします。
まず、小学生の理想的睡眠時間は10~11時間です。
平均的な小学生は、朝7時前には起きると思いますので、
前日の夜は遅くとも9時には寝ていないと、ということになります。
低学年と高学年、さらには個人差もありますので、
一概には言えないところもありますが、
この年代に必要な成長ホルモンは、
寝ている間に分泌されるので、
質の良い、十分な睡眠を確保してあげることが大切です。
中学生・高校生になると、理想的な睡眠時間は8~9時間。
朝7時に起きるには、遅くとも11時には寝ていなければなりません。
この年代になると、だいぶ体力も付いてきているので、
睡眠不足は体力でリカバリーできることもあるのですが、
規則正しい生活習慣を身につけることが重要です。
それと、これは私自身も経験があるのですが、
授業や部活で疲れてしまって、
夕方寝をしてしまうことってよくあるのではないでしょうか。
これ、夜に目が冴えてしまって夜更かしの原因になったり、
夜の睡眠の質を低下させてしまったりと、
良いことがありませんので、できるだけ避けた方が良いです。
体がその時間になると眠くなるサイクルを覚えてしまうと、
なかなか抜け出せなくなるので、
その前に何とか踏ん張って、
夜まとめてしっかり寝るリズムを身に着けたいですね。
睡眠の話はとても奥深く、また日々更新されているので、
まだまだお話したいことはたくさんあるのですが、
今回はこの辺にしたいと思います。
とにかくリズム良くしっかりと、
十分な睡眠時間を確保させてあげて下さい。
本当に「寝る子は育つ」のです。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年06月02日
子どもの睡眠を大切に

「寝る子は育つ」ということわざがありますが、
人間、特に発達の途中にある子ども達にとって、
睡眠はメチャクチャ大事です。
それぞれの教育方針や、
ご家庭の事情もあるのはよく分かっているのですが、
うるせーよ、と言われることを覚悟で言いますと、
ちょっと大丈夫ですか、と言いたくなる場面によく出会います。
例えば、
夜の10時を過ぎてコンビニやレンタルビデオ店に、
就学前くらいの小さなお子さんを連れて来ている親御さん。
やっぱり良くないと思いますよ。
1~3歳児は、昼間起きて夜ぐっすり眠るという、
体内時計の基本をつくる大事な時期。
このメリハリが大事なのです。
4~6歳児は、きちんと昼寝をすること。
まあ、徐々に体力が付いてきているので、
昼寝をさせすぎることにも注意が必要なのですが、
理想的な睡眠時間は、
1〜3歳 12〜14時間
4〜6歳 10〜13時間
7〜12歳 10〜11時間
13〜18歳 8〜9時間
と言われています。
ということは、朝7時に起きるとすると、
遅くとも夜9時には寝ていないと、ってことになりますよね。
で、さらに昼寝を1~2時間。
社会生活基本調査による平均睡眠時間は、
これより少ないようですので、要注意です。
幼児期の睡眠が大切な最大のポイントは、
この時期に最も多く分泌される「メラトニン」をいうホルモンです。
体内時計のコントロール、抗酸化作用、性成熟の抑制作用など、
様々な重要な作用を持っていて、
この時期にメラトニンをたくさん分泌させることが、
その後の健やかな成長に大きく関わると言われています。
睡眠時間がどうこうという話は、
すぐ目に見えて結果が分かることではないので、
ついつい意識をゆるくしてしまいがちですが、
後から振り返ると、影響が大きい可能性が高いので、
要注意です。
ちょっと長くなってしまったので、
小学生以上のおこさんについての話は、次回にしたいと思います。
もちろん、小学生以上にとっても睡眠は超重要なので、
またお付き合いいただければ幸いです。
2018年06月01日
1コマ増設のお知らせ
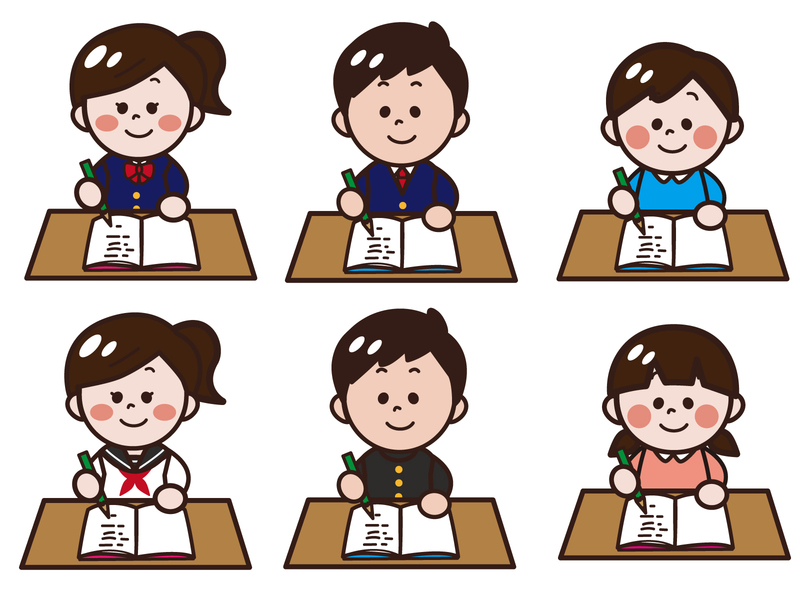
【陽平塾】の現在の開講日は、
月 20:00~21:30
火 20:00~21:30
水 18:20~19:50、20:00~21:30
木 18:20~19:50、20:00~21:30
土 14:00~15:30
です。
おかげ様でどのコマも、ほぼほぼ満席です。
そのため、新たに入会をご希望される方に、
お席を用意出来ないという状態になっています。
そこで、新たなコマを増設することにいたしました。
【【【 月 18:20~19:50 】】】
こちらの日時に新たに開講いたしますので、
多くの(1対4なので4人までですが)生徒さんに来ていただけると嬉しいです。
中3受験生で、総体が終わってから、
とお考えの方も多くいらっしゃると思われますが、
まずは一度、お問合せいただければと思います。
ご連絡先は、090-1882-7129 です。
つながらない場合は、留守電にメッセージを残していただければ、
後ほどおかけ直しいたします。
とりあえず今回は、以上、お知らせいたします。
よろしくお願いいたします!!
2018年05月25日
生徒同士で教え合うのって
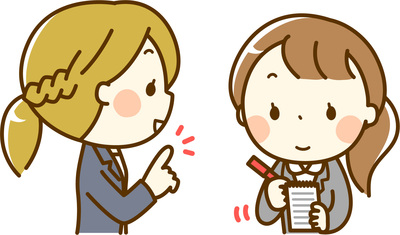
塾の授業中、または、自習室を利用してくれている生徒たちが、
お互いにわからないところを教え合っているというシーンをよく見かけます。
これ、すごく推奨しています。
そういう場面で私が出て行って「これはこうだよ」って教えてしまうことは簡単なのですが、
あえてそうせず、遠目に見ることにしています。
何故かと言うと、2つの大きなメリットがあるからです。
1つ目は、友だちに教えることによって、
教えている本人の理解がより深まるからです。
人に教えるということは、教える内容を本人の肚に落とさないと出来ないことなので、
教える側にとってもかなりメリットがあります。
これは、友だちどうしに限らず、理解できたかどうかを確認する時に、
「じゃ、これ説明してみて。」と生徒に言うことはいうことはよくあります。
2つ目は、先生に教わるよりも、
友だちに教わったほうがスッと理解できることもあるからです。
生徒たちはどうしたって私のことは“先生”として見ていて、
それはそれでいいのですが、
先生から教わるのと、友だちから教わるのって、何だか違うみたいなんですよね。
「いやこれ百万回教えたでしょ!」ってことも、
友だちから教わった時に1回ですんなり理解できた、みたいなことってあるのです。
自己弁護するわけではないですが、
それは教え方の上手い下手とは違った要素なのですね。
だったらそれはそれ、利用させてもらおうという話です。
という訳で、陽平塾はこのような方針ですので、
授業中や自習中のおしゃべりはOKです。
もちろん、無駄話で盛り上がるのはアウトですが、
ルールと雰囲気をしっかり作ってあげれば、
生徒たちは理解してちゃんとやってくれるものです。
ですので、彼らが持っている力を上手くお借りしています。
この辺も塾に通うメリットとお考えいただければと思います。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年05月17日
ゲームをすると分かること

私はたまに、授業中にゲームをしたり、クイズを出したりします。
特に、新しく入会してくれた子の初回授業では、
リラックスしてもらう意味も込めて、ゲームやクイズをします。
もちろんそれは、リラックスやリフレッシュという狙いもあるのですが、
一番の狙いは、そこではありません。
ちょっと大げさに言うと、その子の“人間性”を見ます。
もう少し平たく言うと、その子の、
“目の前にある課題に対する取り組み方”を見ます。
そこで、面白がって食いついてきてくれる子、
ああじゃないこうじゃないと試行錯誤してくれる子は大丈夫。
面白く教えてあげれば、勉強に興味を持ってくれるハズです。
この「試行錯誤力」っていうのが大事なのです。
さらには、
「あ、この子は頭の回転が早いな」とか、
「この子はユニークな考え方をするな」とか、
その子の個性が分かるのも、その後の指導に活かせるので、
メリットがたくさんあります。
しかし中には、初めから「もう無理」と、
投げ出してしまい、考えようともしない子もいます。
みんなとゲームやクイズなどをした時に、
あまり勝ったことがないという経験を積み重ねて、
自信を失ってきたんだろうな、と思います。
そんな子には、まず何かで自信を付けさせる必要があります。
これもまた、その後の指導に活かせるので、
私にとってはメリットなのです。
ご家庭でも、ときにご家族でゲームやクイズをしてみてはいかがでしょう。
「頭の体操」とか、「脳トレ」とかでググッてみるといいと思います。
私もよく使いますが、「数独」なんかもオススメですよ。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年05月16日
英単語が覚えられないのは
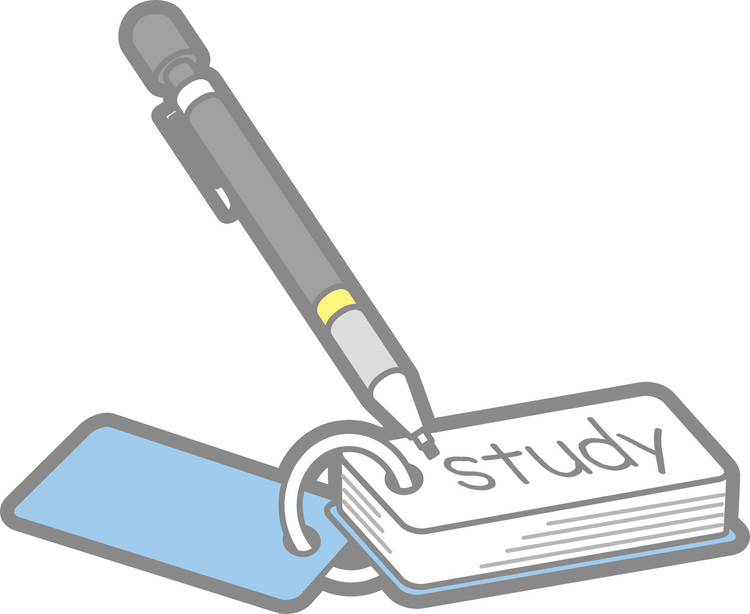
英単語がなかなか覚えられないっていう子、結構います。
英語は、もちろん文法も大事なのですが、
最低限の単語が覚えられていないとなると、どうにもなりません。
英語を学ぶ上で、単語を覚えることはまさにキホンの「キ」。
でも、英語が苦手な子の多くは、ここでつまづいていることが多いです。
そこで今回は、単語が覚えられない原因のひとつを解説します。
単語が覚えられない子って、
ほとんどの場合、そもそも単語が読めません。
すると、例えば「YOU」という単語を書いて練習する時も、
『Y(ワイ)・O(オー)・U(ユー)』
と、頭の中で読みながら書いています。
そうなってくるとこれは、単語の練習ではなく、
いつまでたってもアルファベットの練習です。
「YOU」は「ユー」と、
頭の中もしくは声に出して読みながら書かなければ、
「YOU」という単語としてインプットされません。
ですので、単語の練習をさせる場合には、
まずその読み方を教えてあげる必要があります。
発音は良いに越したことはありませんが、
ともかく読み方が分からないことには、単語の練習にならないのです。
私たちが日本語を獲得してきた過程を考えても、
まずは耳で聞いて、話せるようになって、読めるようになって、
それから初めて書く練習をしてきましたよね。
英語も言語ですから、プロセスは全く同じです。
読めもしないのに書いていても、それは絵をかいているのと同じこと。
もしお子さんに、教科書のいま学校で習っている箇所を読ませてみて、
さっぱり読めないようでしたら要注意。
いち早く単語練習の方法を変える必要があります。
英語はどうしても、こうしたコツコツとした作業が必要ですが、
ひとつひとつ積み上げていくしかないですね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年03月09日
力がつく時
春期講習生&新規入会生 募集中!!

先日、授業でこんなシーンがありました。
ある中学生の男の子が、英単語テストをしていました。
基本、満点を取れるまで繰り返させます。
英単語を覚えるのが苦手な彼は、
すでに数回、テストを繰り返していました。
これで最後、と意気込んで臨んだテストで、
本当に惜しいスペルミスをしてしまい、満点を逃したのです。
すでに何回も繰り返していたことと、
そのミスが本当に些細なものだったので、
30回書き取り練習をして終わりにしよう、と伝えました。
しばらく経って終わった頃かと見に行くと、
彼のノートには明らかに30回以上の書き取りの跡が残っていて、
まだ書き続けています。
聞いてみると、
「30回書いても覚えられないと思ったから、100回書こうと思います。」
これは、と思ってそこにいた生徒みんな(1対4なので4人)の手を止めさせて
次の質問をしました。
「10回の腕立て伏せで、何回目が一番力がつくと思う?」
1回目! 5回目! 10回目!
いろいろな意見が出ます。
でも答えは、12回目です。
伝えたかったのは、言われたことだけやっているうちは、
力なんかつかないってことです。
自分の頭で考えて、必要なことをやること。
この時いた生徒たちは、勘のいい子が多かったのか、
それ以上の説明はいりませんでした。
そして、100回書いていた彼の、誇らしげな顔。
小人数ではあるものの、
複数の生徒を集めて授業することのメリットを感じた瞬間でした。
腕立て伏せの話は、以前、
私が受けたあるセミナーで聞いた話の受け売りなのですが、
自戒の念も込めて、たまに使わせてもらっています。
言われたことだけやっているうちは、大した成長はないってことですね。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2018年03月08日
自分の頭で考えよう
春期講習生&新規入会生 募集中!!

とうとう今年度も高校入試が終わりましたね。
現在、陽平塾は定期面談期間で、
内部生のご父母からいろいろなお話を伺っています。
また、入塾希望のお問い合わせも多くなりますので、
面談の機会が多くなる時期です。
そんな面談の時に、よく出るご質問がこちらです。
「勉強の仕方が分からないみたいなんです。」
私の経験上、このご質問の意味するところは、
「勉強をやる気がないんです。」
と、ほぼほぼイコールです。
何故かというと、「勉強の仕方が分からない」というお子さんは、
それを理由に、勉強をしていないことがほとんどだからです。
自分なりに、非効率であっても、
何かしら考えて取り組んで来たけれど効果が上がらない。
というケースは稀ですね。
例えば、
英単語を覚えようと毎日何度も書いて練習し、
1カ月頑張ったのだけれど、全く覚えられません。
先生、どうしたら覚えられますか。
これだったら話は分かります。
英単語を覚えるために書いて練習するくらい、
誰でも考え付く勉強法です。
でも、それをやっていない。
だから、やる気がないのとイコールだという訳です。
その証拠に、と言いますか、
勉強の仕方が分からないという子は、勉強の仕方を教えて、
教材や日々の勉強時間なども細かく指示を出しても、なかなか実行できません。
その挙句、数ヵ月後の保護者面談でも、同じご質問が出ます。
「まだ勉強の仕方が分からないみたいです。」
ですので、勉強の仕方が分からないという子には、
まず、自分の頭で勉強法を考えさせます。
それで、それにアドバイスなり修正なり加えて実行させる。
自分の頭で解決方法を考えて、
課題を乗り切る力を身に付けさせることが最終目標ですから、
ここを見据えてリードしてあげることが大切です。
キーワードは「自分の頭で考えさせる」です。
それでは今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2017年07月10日
夏期講習のご案内

【陽平塾】では、今年度も夏期講習を行います。
期間:7月21日(金)~8月31日(木)
時間帯:9:00~、10:40~、12:20~、14:00~、15:40~17:10
授業形式:最大1対4までの個別指導
対象学年:小学生・中学生(高校生は応相談)
事前の面談で個別にカリキュラムを設定し、
ご希望の回数を、ご希望の日時に受講していただくシステムです。
夏期講習のみの受講も可能ですので、
受講を検討されている方は、お気軽にお電話下さい。
電話:090-1882-7129(井田)
次回以降の投稿では、
最近の授業で感じたことや、
保護者面談(現在、内部生の保護者面談期間です)での気付きなどを、
共有させていただこうと思っています。
良かったらご一読下さいね。
では、今回はこの辺で。またお付き合いいただければ幸いです。
2017年03月17日
『浦島太郎』についての一考察

日本人なら誰でも知っている童話『浦島太郎』。
亀を助けた若者が竜宮城でもてなされ、帰りにもらった玉手箱を開けるとおじいさんになってしまう、というあのお話です。
なんか昔から腑に落ちないんですよね。
何も悪いことをしていない太郎が、なぜ罰を受けなければならないのか。
ハッピーエンドでもなければ、勧善懲悪でもない。
この話を聞いて、どんな気持ちになればいいのって思ってしまうわけです。
一説によると、
元の話では、太郎はそのあと永遠の命をもつ鶴に生まれ変わったとか、
明治時代に「約束を破ったら罰を受ける」という教訓を示すために、続きの部分をカットしたとか、
いろいろあるようです。
そこで、私なりの一考察。
この話のポイントはズバリ、乙姫様。
乙姫は知っていたはずです。
海の中の竜宮城に流れる時間と、地上を流れる時間のスピードが全く違うことを。
しかし乙姫は、それを太郎に伝えなかった。
帰したくなかった。
太郎を愛してしまったのでしょう。
それでも、やがて太郎は帰ることを決意します。
でも乙姫は知っていました。
地上で太郎を待ち受けているのは、孤独という名の地獄だと。
社会的動物である人間にとって「誰一人、自分を知っている者がこの世にいない」という状況は、耐えがたい苦難。
生き地獄とはこのことです。
そこで乙姫は、太郎に玉手箱を手渡します。
「決して開けてはいけません」と言って。
開けるとどうなるのか、もちろん乙姫は知っています。
つまり玉手箱は、
「苦しみに耐えきれなくなったら使ってね」という、
言わば、自決用の毒薬や爆弾のようなものだったのです。
しかし、太郎は死ななかった。死ねなかった。
乙姫は、愛する太郎を救いたいがために玉手箱を渡した。
でも出来ることなら開けて欲しくない。
たとえ開けたとしても、太郎を殺すことは出来ない。
結局、太郎はヨボヨボのおじいさんになりました。死に近づくことしか出来なかったのです。
若者の姿ならまだしも、家も財産もない天涯孤独の老人になってしまった太郎が、幸せな余生を過ごせたとは、とても思えません。
以上のような解釈から導かれる教訓は、
太郎を帰したくないがために、竜宮城と地上の時差を伝えなかった乙姫のような、
「身勝手な愛情は、相手を苦しめる」
ということ。
さらに、
苦しみを救うどころか、太郎を苦しめることしかしなかった玉手箱を渡した乙姫のような、
「中途半端な優しさは、相手を苦しめる」
ということ。
以上、『浦島太郎』についての一考察でした。
いかがでしょう。
ちょっとネガティブですかね。
さて、文脈とは全く関係ありませんが、
『陽平塾』では、春期講習生・新年度生を募集しています。
春期講習は、3/25~4/3です。
詳しくは、お電話でお問合せください。
電話:090-1882-7129
それでは今回はこの辺で。
またお付き合いいただければ幸いです。